*** コメント入力欄が文章の最後にあります。ぜひご感想を! ***
今回はアーティストという言葉の持つ本来の意味について、少し具体的にお話したいと思います。というのも、ごく最近でありますが、私は日本の素晴らしいお菓子と、それから素晴らしいバイオリン演奏に出会い、まさにこれはアートの世界であるというふうに思ったのです。
そのお菓子というのは、我が国ではもう手に入れることがなかなかできない、一見さんはお断りという高級割烹と同じような仕組みで、販売も限定された人々にだけなされている。しかし、世知辛い世の中で、それをプレミアムの値段をつけて、いろいろなマーケットプレイスに出品する人が、いるようです。自分が非常に大切に思う人から贈られた品物を、そのように本来の定価よりも高いびっくりするような料金をつけて売っているという人たちのえげつない心にもすごく残念に思いますが、現代におけるアーティストの置かれた位置、あるいは地位といってもいいかもしれません。それについて考えさせられる場面でした。
そのお菓子というのは、口に入れたら本当にとろけるような、風雅なという、そういう平凡な言葉で表現することができないほど美味しいお菓子でありまして、甘いものに飢えていた私の戦後の少年時代であれば、バクバクとそれを食べたであろうけれども、もうそのようにバクバクと食べる食欲が全て失われた。もう私は今、嚥下障害という病気を背負っていて、食道が手術の後遺症で狭窄している。細く閉じてしまっているわけですね。ですから、ほとんどのものが喉を通らない。そういう狭窄した喉にあっても、自然に口の中でとろけていく。飲み込むというようなことを意識しなくても、口の中に広がる豊かな風味、それが私は幸せにしてくれる。そういう素晴らしいお菓子ですが、そのお菓子が普通にはもう手に入らない。その手に入らないお菓子がインターネットで販売されているという実態を知って、本当に悲しくなりました。そのお店の職人さんたちは、そういうことに対して、誇りに思うどころかものすごく残念に思っていることだと思います。自分の心を込めて丹精して作った商品を、理解できる人におすそ分けしたい。そういう気持ちで作っていられるに違いないと思いますが、それをよりによって自分の端金のために心を売り渡す人々が存在しているんだということに、本当に悲しく思う次第でした。
でも、そういうお菓子を、店を大きくしたりとか、お金儲けをしたいとか、有名になりたいとか、という気持ちではなくて、少しでもこの味を理解してくれる人のお手元に届けたい。その職人魂、まさにアルス、英語で言えばアートに生涯を捧げる職人さんたちの心意気だと思いました。職人、昔で言えば「士農工商と」言われたに「工」に相当する部分かもしれませんけれども、そういうところで、自分の行くべき道を見誤らずに、きちっと見据えて頑張っている人がいるということは、同じ日本人として、同じ日本人というのはいささかおこがましい気もいたしますが、とても誇らしく思う次第であります。
日本の中にはそのような伝統を守るというだけではなくて、伝統をより良いものとして発展させる創意工夫を弛まずやっていく誠実な職人魂が生きている。これは、本当に素晴らしいことであると思います。こういう職人魂っていうのは決して日本だけのものではなく、国際的に見ても、職人さんたちの素晴らしい技の世界、そして技にかける心意気、それはほとんど万国共通のものであると本当は思います。特に私達の身近にそういうものが存在するということは、私達の文化が決して広告資本主義の世界にまみれているのではないということのかすかな証として、希望として私には映ります。
もう一つ職人さんたちということで言えば、私は音楽に関して非常に無教養でありまして、多くの演奏家の名前を知っているわけではありません。国際的に超有名人の方の演奏を聴くというのが精一杯のところでありますが、最近インターネットのおかげで、全くそれまで出会ったこともない方の演奏に出会うという機会に恵まれ、昨日はたまたまMaría Dueñas(マリア・ドゥエニャス)っていうふうにおっしゃるんだと思いますが、多分スペイン語のスペリングなので私の発音でそれほど違ってないと思いますが、その人の演奏を聞いて、本当に若くて綺麗な人であるのに、その音楽の解釈の骨太さ、深さ、確かさに心打たれ、また技術的にも素晴らしい磨きをかけた、本当に天才的なバイオリニストだと思います。バイオリニストの中には天才的な人がいっぱいいるんですけれども、このMaría Dueñas(マリア・ドゥエニャス)っていう人は、おそらく21世紀を牽引する、本当に素晴らしい演奏家であると思います。
芸術の世界はアーティストに過ぎないと言われてしまいそうですが、何もわからない大衆に対して、音楽の楽しみを届けることを使命としている。言ってみれば、本当に大きな尊敬を受けることのない、いわば大衆を相手にした芸術家だと思いますが、そういう大衆を相手にしているということの屈辱を感ずることなく、自分のアートを磨いていくアーティストの真骨頂を、その方の演奏に私は感じ入り、皆さんにも紹介したいと思うんです。こういう広告資本主義の汚らしい世の中の中にあって、本当に一輪の花として咲くことに誇りを感じて頑張っている。そういう人がいるということは、何よりも大きな励ましであり、またときに慰めであると思うんですね。María Dueñas(マリア・ドゥエニャス)の演奏は、私はたまたまメンデルスゾーンで最初にそれに接し、メンデルスゾーンだったらこういうふうに弾くことはわかるなと思ったんですが、メンデルスゾーンだけじゃなくて、ブラームスや、バッハの無伴奏にも挑戦していて、それがものすごく素晴らしい演奏なんですね。単に技術的に素晴らしいのではない。バッハを読み込んでいる。楽譜を読み込んでいる。そういう演奏家の素晴らしさがある。そしてものすごく軽い音楽、ヴィヴァルディの四季であるとか、そんなものも弾きこなしている。そういうときにはもちろん力が入っていない。それは皆さんを楽しみの世界にいざなうかのような、遊びのようなものでありますけれども、それを艶やかに演奏してくれる。その幅の広さと技術の確かさ、そして何よりも楽譜というものを何回も何回も読んで、作曲家の真髄に迫ろうとしている。その音楽力の素晴らしさ、音楽力っていう言葉が適当かどうか甚だ自信がありませんが、音楽性の豊かさといった方がいいんでしょうか、そういう単なる表面的な技術の素晴らしさではない。暗譜している楽譜を弾いている曲芸でもない。本当の音楽の素晴らしさを伝えてくれる素晴らしいものであると私は思いました。
そこで皆さんに、アートの世界というのは、学問の世界、哲学の世界あるいは数学の世界とは違う、言ってみれば技の世界であるんですが、技の世界は技の世界として素晴らしいものがあるんだということ。これを現代文明では、こういう文化をきちっと保っているのはドイツではないかと思いますが、ドイツではよく言われているように大学で学者になるとか、医者になるとか、あるいは法律家になるとか、そういう道の他に、大学ではなくて、マイスターになる、職人になるっていうコースがありまして、マイスターにあるということは、大学を出て専門の職業に就くのと同じように尊敬される。皆さんはMeistersänger(マイスタージンガー)という曲をご存知だと思いますが、ジンガーは、英語で言えばsinger、歌手ですね。歌手であってもマイスターである。マイスターであるということは職人頭だということですね。本当に職人としての歌手、これがドイツでは尊敬される職業の道として未だに多くの若者の憧れになっているわけです。
日本やアメリカのように誰でも彼でも大学に行くという馬鹿げたことが、大学をビジネスとして展開する大学経営者の餌食になっている。そういう世界とは全く違う世界が、今現在の21世紀の現在も、ヨーロッパの大国ドイツには脈々と生きているっていうこと。これを皆さんもぜひ知っていただきたいと思います。日本ではマイスターという言葉こそありませんが、職人気質という頑固な職人道一徹と言われる世界において、「自分の技がわかってくれる人にわかってもらえばそれで十分だ。それで有名になりたい、金持ちになりたいというわけではない」という人たちが、存在するんだっていうこと。これは大きな慰めであり、私にとっては本当に大きな激励となるものです。
私もできたらそういう人たちに、数学の楽しみを伝えたい、お届けしたいと願いますが、数学はお菓子と違って、本当に多くの人を普遍的に喜ばす魅力にあふれているとは言えません。数学の魅力を理解してもらうために、せめて口の中に数学を入れてもらう。そのことで努力しなければならない。そういうところで、数学はハンディキャップがあると思いますが、一度口に入れた途端にこれがどんなに美味しいお菓子以上に美味しいものである、とその美味しさをきちっとお届けできるようなお話をしていきたいと、心から思う次第です。というわけで、今回はアートとかアーティストっていう言葉が、現代日本ではすごく軽々しく誤解されて使われておりますが、そういう職人の世界の持っている素晴らしさを私達時々思い起こさせるのに、アーティストという言葉の意味について理解することも大切ではないかと思い、こういうお話をさせていただきました。
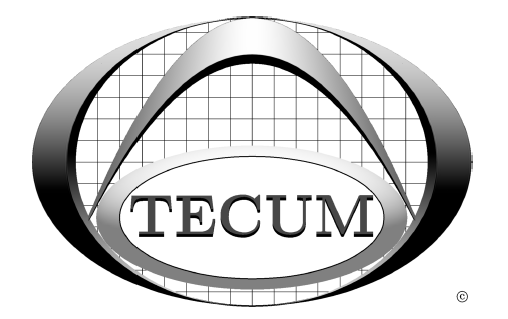
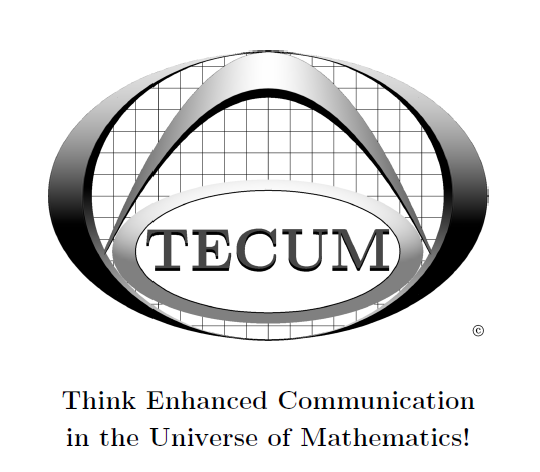

コメント