*** コメント入力欄が文章の最後にあります。ぜひご感想を! ***
今回は少し話題を変えて、私が初めて海外に行ったときに大変驚いた経験についてお話したいと思います。それは、パリでだったと思いますが、道路にいわゆる日本で言うところの乞食という人が座っていまして、その人たちが非常に才能がある。チョークで、舗装した道路に絵を書いているわけですね。絵を書く才能のない人は、美しい文字を書いている。文字でありますから私でも読むことができて、その文字には、「私にパンと葡萄酒を恵んでください。」そう書いてある。パンはともかくとして、乞食の人がワインをねだるなんて日本ではとんでもない、というふうに思われるわけですが、そのパンによって1日の生を存え、1日の命の水を飲むことができるのであるから、というふうに書かれている。乞食であっても、ワインを一杯飲むということが、いわば人間としての本当に最小限の権利である。権利っていう言い方は全くしてないんですが、そのように「哀れな私に一杯のワインを恵んでください。」そういうふうに書かれていたことが、とても良い印象的でした。
日本では、貧しい人が酒を飲んで昼間から酔っぱらうなんてとんでもない。そういう厳しい倫理感が社会で一般的ではないかと思うのですけれども、ワインを飲むということが、言ってみれば人間が生きるための最低限の基礎であると。そういうことが社会に共有されているっていうことに大いに驚いたわけであります。パンとワイン、これは人間の生命を繋ぐための本当に生命線であるという認識が、私達日本人には欠けていたっていうこと。
また私はフランスで大学をいくつか訪問しましたけれども、学生食堂に寄ったときに、ワインは水と同じように飲み放題であるということ。それにも驚きました。教授用の食堂っていうのが、ドイツの大学やイギリスの大学では当たり前のようにしてあるわけですが、そのような教授用の食堂には、本当にそれはそれは高価な立派なワインが秘蔵されていまして、オックスフォードとかケンブリッジとか古い歴史を持つ大学には、今日教授用のワインセラーというのがある。教授が、学問的な権限を持っているというだけではなく、学問的な権威を人々が尊敬して、その教授にふさわしい立派なワインを提供するという文化が存在しているということに本当に驚きました。
collegeとかuniversityという言葉に関する日本の誤解、これがひどいものであるということをオックスフォードやケンブリッジのcollegeを参観して、つくづく思いました。collegeを短期大学って訳す日本の英文法学者の無教養ぶりに、本当にがっかりしました。アメリカのCommunity Collegesみたいなものと、イギリスのcollegeを全く誤解しているという、とんでもない誤解の上に成立しているものだと思います。アメリカのCommunity Collegesっていうのは、日本で言えばちょっとその辺の教養講座というか、一応大学の体を成していますから、短期大学というふうに訳すのがいいのかもしれませんが、全く意味が違う。そういう言葉を日本人が、文学を専門としている人たちでさえ全く理解してないっていう現実に、怒りを通り越してあきれ果てたものであります。
海外に行ったときに、受けた大きな衝撃っていうのは、それだけではございません。私が本当にびっくりしたのは、毎週週末、その辺のCathedral大きな教会では、ほとんど毎週、生演奏の会が催されるわけです。教会で奏でられる音楽っていうのは、また格別の響きを持っていて、素晴らしいものであります。特にオルガンが入ったとき、あるいは室内楽だけのときでも、特別な音響効果に恵まれて、本当にそれは心休まるときであるわけですね。その演奏家が超有名人であるということが、あるかどうかっていうことはあんまり本質的ではありません。超有名人がそういうコンサートに参加してくださることもあるのですが、それは例外的でありまして、町の音楽家という人々だと思います。その町の音楽家が、コンサートを開く。コンサートのチケットが、町の人々によって買われて、そして成立するという文化に私は本当に心の底から羨望を感じました。
日本では音楽家が立派なコンサートホールを借りると、そのコンサートホールの費用だけでも捻出するために、チケットを演奏家自らが自分の弟子に割り当てて、ばらまかねばならないという寂しい状況、非常に情けない状況を知っているだけに、ヨーロッパの芸術が本当に人々の生活に密着しているんだっていうことを痛切に感じました。そして、その演奏はというと、もちろんそんな非常に優れた演奏家のものでありませんから、間違いもありますし、決してエクセレントっていうわけではありません。でも、本当の生演奏の持つ力というのは、ちょっとしたミスとかっていうことは全く無関係に、人の心を打つものなんですね。そして、その後に拍手・大喝采がある。その拍手・大喝采というのは、その名演に対する感謝というよりは、名演を褒めたたえるというのではなくて、本当に自分のうちの心からなる感動を、その感動を与えてくれた演奏に対して感謝の気持ちである。これは一種のチップの文化であって、自分が大きな感動を得たならば、その感動を得させてくれた人に対して心からなる感謝を表現したいということなんですね。
他方、我が国の演奏会はというと、演奏会やるたんびに必ずBravoというような、Bravissimo、そういうような声がかかる。毎回大成功であるかのように思われていますが、私は日本の演奏会にずいぶん参加しましたけど、これはとても立派な演奏会とは言えないという演奏会も、残念ながら少なくありませんでした。でも日本の演奏会は必ず成功する。もう本当に、絵に描いたように成功する。それはとてもおかしなことだと思います。演奏会は、観客と演奏家が一体となって作り出す、いわば劇的な空間。それを共有したときの喜びだと思うのですが、それが必ずしも成功したとは言えないという演奏に出会うことが少なくありません。日本では有名な人が来れば必ずいい演奏会ができる。そういうふうに思っている人がいるのではないでしょうか。すごく音楽とか芸術が形式ばっていて、一部の評論家と言われる人々が絶賛すると、それだけで素晴らしい演奏会だっていうことになってしまう。
演奏家はともかくとして、評論家が果たしてきた歴史的な役割に関して言えば、むしろそれは悲惨と言っていいような代物でありました。かつての絵かきの方の苦労を思い出せば明らかでありますけども、芸術の権威として君臨していた人々は、ろくでもない評論をすることによって、新しい演奏、新しい芸術、それが登場してくるのを妨害することはあっても、決して育てることはなかった。本当に評論がむしろ芸術の漆喰になっていたという過去の歴史を思い出せば、芸術家あるいは評論家と言われる人々は、もっともっと謙虚であるべきだというふうに思います。
私は、評論というものを非常に低く評価しておりましたが、かつて小林秀雄の評論を読んだときに、評論は芸術以上に芸術的である。そういうふうに感じまして、評論というものを、決して芸術に劣らない鋭さを持っている。そういうふうに思いましたけれども、それ以降の評論はどちらかというと、出てきた人の評価を褒めたたえる。そうすれば危険はないということでありますけれども、評論家自身がリスクを背負っていない。言ってみれば、べた褒めの評論に堕落してしまっている傾向を少し感じて、残念に思っています。
日本では、国際的に著名な演奏家とかっていうレッテルを貼られると、それだけで立派な演奏になっているように、みんな思っているんですけど、私に言わせれば、とんでもない話でありまして、本当に立派な演奏というのは、技術的に上手だとか、音符を正しく追えるということではなくて、心を打つということなんですね。本当に心が揺さぶられる演奏っていうのはある。私はその典型例を一つ挙げるとすれば、イツァーク・パールマンのバイオリンだと思います。一番わかりやすいこんなに心を打つ演奏というのがあるんだということをイツァーク・パールマンによって、知るわけであります。イツァーク・パールマンはイスラエル人ですから、イザーク・パールマン、そういうふうに発音するが正しいのかもしれません。彼はジュリアード音楽院というところに招かれて、その中で頭角を現すわけですが、そのイツァーク・パールマンが、ジュリアード音楽院で習ったとき、そのときに、楽譜を見て、「ここになぜフラットがつくのか、その意味を考えろ」と、そういう教育を受けて、彼は当惑したそうです。そして、そのような教育を通して、彼は楽譜を理解する、楽譜を解釈するということを初めて学ぶわけで、彼はその後、自分たちもあるいは自分も後輩に対してそのような指導をしている、とインタビュー記事を見たことありますけれども、結局のところ、「この演奏家は何をしようとしているのか。この演奏家が実現したいというものは何なのか」とそういうことを、パールマンは考えたんだと思います。
それは、数学者と同じでありまして、出来上がった数学は、できあがったスコアと一緒なんですね。楽譜と一緒。でも楽譜が同じでも授業の仕方は全く違う。その授業においてどのような感動があるのか。どのような感動が用意されているのか。そのどのような感動がどのように広がっているのか。そういうことを理解して授業できる人は、一種の独創的な演奏家なんだと思いますけども、楽譜の通りに綺麗に演奏する。こういうようなものは、私は芸術とは縁もゆかりもない。それは電子音楽に過ぎないと私は思うんです。
最近若い人々が活躍著しく、特に女性の演奏家が素晴らしいですね。そして自由奔放に音楽を解釈している。そのような彼女たちの凄まじいアクティビティを見ると、私は心から感動します。それは、ラフマニノフという演奏家の曲を弾きこなしているということではない。そうではなくて、ラフマニノフを、彼女たちが自らラフマニノフに乗り移って演奏している。そういうことの感動だと思うんです。
そういうように本格的な演奏家が活躍する中にあっても、日本で残念なのはクラシック名曲100選とか、クラシックバイオリン100選とか、そういう基礎的なものを勉強すれば何とかなると思っている人がどうも数少なくない。確かにそういう基礎も役に立つかもしれませんが、私に言わせればそれは「少年少女科学物語」のようなものでありまして、そのようなもので心躍る少年少女もいるかもしれませんけれど、科学というのはそういうものではない。勝手に非常に漫画的に、子供らしく理解できるように説明したもの。昔の英雄的な科学者の物語、野口英雄伝とか、エジソン伝とか、私も読みましたけど全くくだらないですね。「そういうものによって、科学に近づけるわけではない」という厳しい現実を人々は知るべきです。
そういう人に私がおすすめしたいのは、どんな人でもいい。立派な人の演奏を何回も何回も繰り返してごらんなさい。1回目はなかなか理解できないかもしれない。2回目に少し理解ができるようになるでしょう。そして、3回目にそれを聞いたときに、自分が今まで聞こえなかった音が聞こえるようになるでしょう。4回目、5回目、6回目、繰り返すことによって、その演奏の鑑賞がますます深いものになる、と私は思います。それをわかったような解説を聞いて、そして自分でわかったような気になるのは、「少年少女科学史物語」を読んでわかったような気になると同じように、所詮偽物であるということです。手っ取り早くリーダースダイジェストのようなもので、クラシック音楽の世界について造詣を得たいと思う人の気持ちの哀れさ。私もよく理解できますけれども、そのようなときに「急がば回れ」という古人の英知に満ちた言葉を、皆さんとともにかみしめる必要があると思います。本当に良いものに何回も触れれば、最初のうちは多分聞きづらい音楽かもしれません。ゴダールの音楽は、ベートーヴェンやショーパンなど比べると、最初のうちは取っ付きづらいかもしれません。でも、取っ付きづらさを我慢して聴いている。その忍耐が、ただの忍耐ではなく、喜びに繋がってくる。そういう大きな喜びに繋がる勉強であるということを、理解してほしいと願っています。
安直なものには、安直な喜びしかない。そして安直な喜びで満足した途端に、その人の理解も安直な範囲を超えることは決してないということです。ぜひぜひ本物に出会っていただきたいと思います。本物と言ったからといって、超一流の芸術家のもの、それに触れる必要ないと思います。でも演奏家が本当に心を込めて、自分の名前を出して演奏している。そういう曲に出会うということは、人生の幸せの第一歩に繋がることだと思います。「安直な努力は存在しない」という当たり前の教訓を引いて、このお話を終えたいと思います。
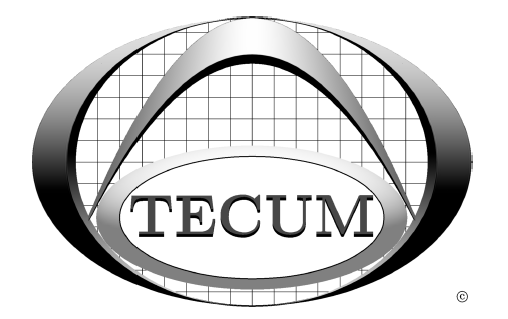
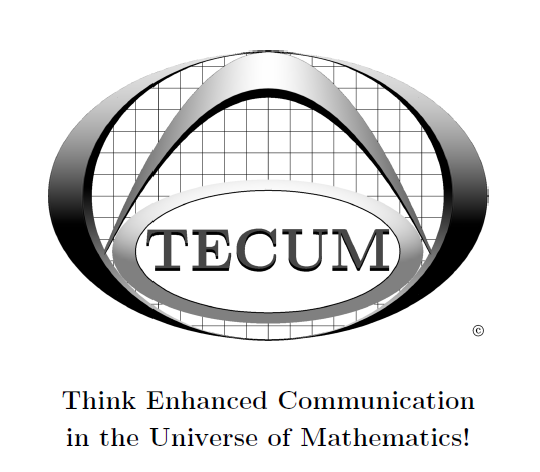

コメント