*** 音声がTECUMのオフィシャルサイトにあります ***
中国の史記という有名な本に載っている話に由来する“鶏口牛後”という言葉について、お話ししたいと思います。「鶏口となるとも、牛後となるなかれ。」直訳すると、鶏口というのは、鳥の口、鳥の頭だという話もありますが、私は中国文学に造詣がないので、本当のところはよくわかりませんが、「鳥の頭、あるいは鳥の口となることは良しとしても、牛後となるなかれ、大きな牛の尻尾になるようでは駄目だ」ということなんです。
この言葉は、我が国ではしばしば、小さな組織のトップになる、あるいは小さな集団のトップになるということは、大きな集団のビリになることよりはいい。こういうふうな意味で使われているようです。確かに、本当に大きな組織、会社、学校でもいいんですけど、それでビリッケツにいるよりは、小さな組織の中でトップランナーであるということの方が、人が育つという可能性は大いにありますね。
例えば学校、最初から都会のマンモス校、その中には小洒落た子供たちもいっぱいいる。いろいろな先進的な情報が発信される。そういうのと比べると、田舎の分校で、学校が全員で10人しかいないという学校で育てられるということの方が、子供にとって幸せだ。これは十分ありうることであると思います。他方、「井の中の蛙」という表現もありまして、田舎の中でものすごい秀才として鳴り響いた。10人くらいしかいなければ10年に一度出るような大秀才であるというふうに、褒めそやされるっていうこともあるかもしれませんが、そういうふうにして得意なってきた子が、少し街のあるいは都会の大きな学校にやってきて、全く通用しない。そういう自分を発見するということもありうることだと思うんですね。それはまさに井の中の蛙であったっていうことかもしれません。
ちなみに私は前にもお話しましたが、長野育ちでありまして、長野の田舎で、私の頃はベビーブームという時代でありましたから、小学校もひとクラス50人以上でありましたが、とっても楽しい小学生時代を過ごしまして、本当に楽しかったのですが、小学校6年生のときに横浜に転校しまして、長野の田舎から来た山猿というふうに友達にからかわれ、何にも勉強もわからない。都会の子供たちは、本当にいろんなことを知っている。いろんなことを知っているということはもうびっくりするほどいろんなことを知っているんですね。大化の改新が645年である。小野妹子とか中大兄皇子とか中臣鎌足とか、私はそのときの受けた文化的な衝撃を未だに忘れません。聞いたこともない言葉が、友達の間で飛び交わされている。すごいことですよね。私は長野の山の中で、横浜の人から見れば、「長野の山の中で暮らしていたんだ。そういう猿のように暮らしていたんだろう」と言われたんですが、私はそのように言われたときに、信州の私の家の裏山で、よく登ってそこでターザンごっこなんかをしてよく遊んでいた生活を本当に懐かしく思い出し、みんなああいう楽しい生活をしたことがないんだな、と横浜の子どもたちに同情したものであります。
そういうときに私を「井の中の蛙」であったと言う人もいるかもしれません。私は長野で楽しい毎日を送っていた。しかし、日本全体の中では、そういう平和な小学生時代を送っているっていう子どもはむしろ少数で、中学受験のためにいろいろな事柄、電気抵抗の計算の仕方とか、そういうのを丸暗記する。そういう子供たちがいたということは、実に驚くべきことで、私はそのときに目覚めるわけですね。そういうのが勉強なんだと一度思って、それこそ並列抵抗の計算の仕方とか、直列抵抗の計算の仕方を理解しようとする。しかし、それを丸暗記するだけだったら簡単なんですね。勉強ってのは難しくない。ただ退屈なだけなんです。
私自身は、その浜に転校したときに出会った衝撃、それは井の中の蛙が都会に出てきてびっくりしたと表現することはあまりふさわしくないと思うんです。むしろ私は、健全な世界にいた人間が、急に不健全な、全く馬鹿げた世界に突然連れてこられて、異なる生き方を強いられる。いわば人生のショックですね。衝撃的な出会いで、これが私の人生に大きな影響を残した。と、こういう言い方は正しいけれど、長野でちやほやされた人間が横浜に来たら通用しなくなったということで、もし“鶏口牛後”を使うなら、全くおかしいと思うんですね。私は、長野でも決して勉強が得意なわけではありませんでしたから、長野でも鶏のしっぽだったかも。そういうふうに言ってもいいかもしれません。でも、私は決して無意味な勉強に毎日駆り立てられたわけではなく、私は毎日充実して過ごしていたわけです。私のように、楽しい青春時代というか少年時代を過ごした人が横浜にはいなかった。横浜の方をもし大きな組織と例えるとすれば、大きな組織は本当につまらない子供たちばっかりだった。そんな気がするんですよ。もちろん中には親友もいっぱいいました。でも概して、少年時代の過ごし方っていう点で見れば、つまらない生き方をしていたんじゃないかな。そういうふうに思います。
一方、私は大学に入って、中学校・高等学校と比べると遥かに大きな集団のわけですね。普通の意味では、小さな村から大きな町にやってきたということですから、鶏口だった人にとっては、牛の尻尾になるというような経験に映ったかもしれません。しかし、私にとっては、その大きな集団の中で優れた人と出会うということは、本当に大きな喜びでした。自分よりも遥かに優れた友人にいくらでも出会うことができる。私が全く興味を引かなかった分野のことに、夢中になって勉強している人がいる。これは私にとって、とても大きな刺激でありました。ですから、鶏口牛後っていう言葉をもし私なりに解釈すると、「小さな世界で自分がトップだということでうぬぼれている。それで、自分の人生が勝利だと思っている」人がいるとすれば、大きな社会に出て、自分がいかに小さな存在であるかということを思い知らされるという経験、もしそういうものに全く恵まれないならば、気の毒だと言わざるを得ないと思うんです。私は決して大きな集団がいいと礼賛するつもりはありませんが、けれどもやはり、本当に優れた人、素晴らしい人、決して叶わないと思い知らされる人との出会いが、人間を成長へと駆り立てる大きな駆動力になるんだと、私は思うんです。
時々、この年になりますと、本当に惨めな人生を生きてきた人に出会うことが少なくありません。やたら威張り散らしている、やたら威張り散らしているということが実際はコンプレックスでしかない。そのコンプレックスを、人をいじめることによってしか満足させることのない、そういう人に出会うことが少なくありません。本当に愚かだと思うのですが、要するに鶏口牛後がうまく働いていない。つまり、自分が大きな組織の中に行ったら全く相手にもされない存在。学問をやっても一流の人間として生きていけるはずがない。そういう人間が、あの人よりは自分の方が上だと、たまたま着いているポジションを利用して、偉そうに振る舞う。こんな恥ずかしいことはないと思うんですね。人間として最も惨めなことだと思うんです。結局のところ、その人は、大きな世界の中に行き、全く自分の力が通用しないっていうことを思い知らされて、そして、その後、小さな組織の中に行き、自分がその中で一番だということで、権力を振るって他の人をいじめている。情けない人生だと思いませんか。
私は、牛後ということ自身が素晴らしいというわけではありませんけれども、一流の人に出会い、自らも少しでも一流の人に近づこうと思う努力をすることが、人生の生きる幸せで、自分がこの組織の中では一番偉いと言われるようなところに行って、いい加減に生きている。人をいじめて、自分が偉そうに振る舞うっていうことでもって自分が偉いと思って、そういう錯覚に陥る。コンプレックスから、劣等感から解放される。そういうふうにしてんだとすれば、本当に馬鹿げた話ですよね。私はその人たちは鶏口でさえないと思うんですね。鶏後、鶏の尻尾、そういうふうに言うべきだと思うんですが、最近日本が社会全体として、何となく自分なりの力を、自分なりの個性を発揮すればそれでいいんだと。そしてそれぞれの個性を尊重することが大切だ。そういう掛け声ばかりが先行して、本当に優れている人を優れていると尊敬できない社会になりつつあるんじゃないか。そして、つまらない権力、身分の職員の上下関係、そういうようなものを後生大事にしている。人の事を中村さんとか、鈴木さんとか呼ぶんじゃない。課長とか、部長とか、あるいは係長とか、そういうふうに呼んで、その序列の中で生きている。全く馬鹿げたことのように私は思うのですけれども、皆さんはいかがお考えでしょうか。
どんな小さな会社に行っても、社長って言われるのは嬉しいんだ。大きな会社に行って万年平というよりはずっといいんだ、という考え方があります。これは、日本とか中国とか意思決定システムの弾力性を欠く社会においては、そういうことが言える面もなくもないと思うのですが、アメリカの大学に行って私が本当にびっくりしたのは、学生が教授のことをファーストネームで呼ぶ。私が最初びっくりしたのは、ジョンって学生が教授を呼ぶ。有名な先生なんですけど、その有名な先生もジョンと言われて何も気にしてない。そういうことを本当にびっくりしました。ヨーロッパで、「日本では親子に対して、親は子供に対して呼び捨て。子供は親に対して必ず尊称を、赤ちゃんの頃はパパとかママとか呼ぶけれども、大人になったらば対等ではなくて、必ず家父長的な文化がある」ことに対して質問されて、本当にそうなのかというふうに聞かれて、聞かれたこと自身に私はびっくりしましたけれど、日本は何かつまらないそういう上下関係にこだわって、それにすがって生きているって言う人々が少なくないということを、最近また思い知らされる事件がありまして、こんなお話をさせていただきました。
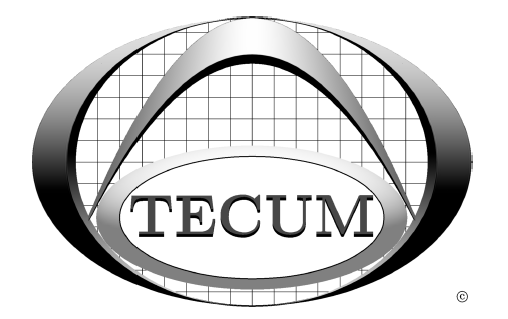
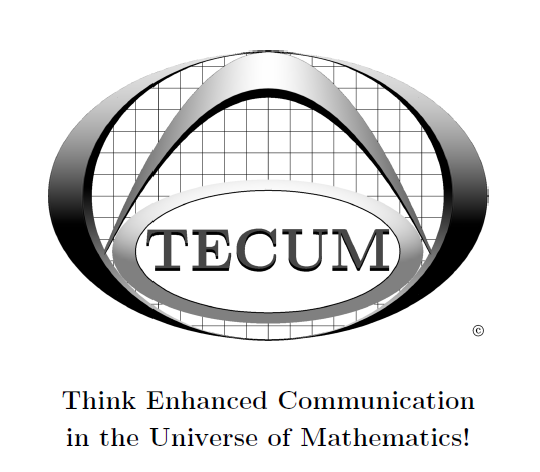

コメント