*** コメント入力欄が文章の最後にあります。ぜひご感想を! ***
昨日たまたま見かけた子どもたちの遊びの風景で、はっと気がついたことがあります。今日はそのお話をさせてください。
小学校の中学年というんでしょうかね、おそらく3年生くらいではないかと思いますが、2人の少女が学校からの帰り道を2人でお喋りしながら帰っている最中でした。その子たちがものすごく楽しそうに遊んでいるんですが、何を遊んでいたかというと、春の強い風に吹かれて、マスクをひらひらさせていたんですね。マスク自身はそんなに遊び道具としては面白いものとして作られたものではありません。しかし、その子どもたちは、自分のかけていたマスクをちょっと手でかざすと、強い風にあらおられて、それがひらひらと動く。まるで風車のように動く。そのことを発見して、2人で喜んでそれを遊んでいたわけです。実にたわいない遊びだと思いますけども、こんなことの中にも、楽しさを発見する子どもたちの想像力の素晴らしさに心を打たれました。マスクが風にひらひらする、その姿が面白いということを、彼女たちは発見したわけです。これこそ、人間的な知性だなと思いました。
マスクなんて鬱陶しいだけで何も楽しいもんじゃない。大人はそういうふうに思っています。場合によっては化粧を隠せて便利である。歯並びの悪いのが見えなくて便利であるとそんなふうにしか考えてない。私もその1人です。海外では、特にアメリカでは、あるいはヨーロッパでは、マスクをして人前に出るということが、何か悪い心を持っているのを見透かされないように、隠している。そういうように映るようで、マスクをするということが一般に嫌われるわけですね。それはちょうど日本において、サングラスをかけていると怪しいと思う人が多いのと同じですね。アメリカヨーロッパの国々では、子どもでさえサングラスをかけたりしている。サングラスをかけるということは決して後ろめたいことではないということです。マスクとサングラスが正反対になっているのがおかしいとしばしば指摘されますが、その鬱陶しいマスクを子どもたちが風にたなびかせて楽しんでいる。すごいことだと思いませんか。発想の大転換というか、大したものではないかもしれませんけど、そんなことは夢にも考えませんでしたね、私自身は。こういうのが遊びだと思うんです。
人間を定義する定義の仕方はいろいろありますね。“ホモサピエンス”知恵ある種っていうことだと思いますが、その知恵があるということはどういうことなのかということは、あまり語られてない。私達は、ですから、Artificial Intelligence、AIというものに対しても、機械で文章が作文されるというようなことを見て、すごいと思ったりする人もいるんですが、馬鹿げた文章で、とてもそれが知性的な文章であると私は一度も思ったことがありません。しかし、文章を書いたことない人から見れば、こんなふうに文章が書けるなんてすごいと、思うのかもしれませんね。機械がそのように人が書いたような文章が書けるってことはすごいかもしれませんけど、技術的にすごいことであって、知性として人間に接近してきたというふうには私は全く思わない。真似事がうまくなってきたというに過ぎない。知性とは縁もゆかりもないと私は思うんです。
機械ができることは、所詮計算のような機械的なことだけ。それが、Generative AIと言おうと何と言おうと、所詮機械がやっていることなんですね。それに対して人間は、マスクを遊び道具にする。こういう発想って素晴らしいと思いませんか。そのときに私は、人間の定義として、人間は遊ぶと動物である。あるいは、遊びを作り出す動物である。あるいは、遊びを楽しむ動物である。遊びを発見する動物である。と、そういう定義が定義としてぴったりしているな、と思いました。全く無駄と思われること、大人から見れば楽しくも何でもないということの中に喜びを発見する、そういう動物。類人猿の中にはそのようなものもありうるというふうに指摘する人もいるでしょう。実際に生まれたばかりの動物が兄弟でじゃれ合っている姿を見ると、人間の子どもとよく似ている。だけど、人間が決定的に違うと思うのは、本来の目的で作られたもの中に違う目的を見出す。そういう創造的なところ、これが素晴らしいと思うんですね。
反対に言うと、よく私達は子どもたち用文化というのを、勝手に大人が作って子どもたちに与える。おもちゃを大人が作ってあげる。プラスチックとかでできたおもちゃ。そりゃあ、子どもにとってはものすごく魅力的な、刺激的なおもちゃだと思うんですね。そういうもので遊ぶ。これは、子どもたちを、言ってみれば機械のロボットに任せて、子育てロボットとして、おもちゃを使っているというに過ぎない。子どもがテレビを見る子ども番組ってありますね。いい大人が、子どもたち向けの番組を作り、子どもたちの人気を得ている。そしてそれがビッグビジネスにまで結び付いている。こんなことって、本当に子どもを幸せにするんでしょうか。あるいは、最近は遊園地も本当に巨大化してきて、大人も子どもも一緒に楽しめるってこんなことをキャッチフレーズにするところもあるんだそうですが、子どもと大人が一緒に遊ぶということが、本当に子どもたちにとって楽しいことなんでしょうか。
私は昨日の風景の中に、子どもが大人とは無関係に、自分たち自身で新しい遊びを発見したときの喜び、その笑顔発見して、これこそ遊びだっていうふうに思ったんですね。今、遊園地やらコンピューターゲームやら、あるいはテレビ番組やら、子どもに迎合する、そして子どもの人気を得れば商品が売れる。そういうふうにして、大人たちのビジネスとして子どもが使われている。子どもが遊びに向かう本当に人間的な喜びの機会が、むしろ剥奪されて、大人たちのビジネスの世界に子どもの遊びが占領されている。そういうふうに私は感じてしまったのですが、皆さんはどうお考えになりますか。
大人が子どもの面倒を見る。これはとても大切な大人の義務です。しかし、私達は子どもたちから本当の遊びを奪ってないでしょうか。あるいは子どもたちを大人の遊びに引き込むことによって、大人たちが利益を得ている。その子どもの遊びを開発する人たちはそれを売ることによって、そしてそれを買う親たちは子どもの世話をいっ時そのおもちゃ、いわば子育てロボットに委ねることによって、自分の時間を作る。でも本当に大切なのは、子どもたちが子どもたち自身の遊びを発見することである、と思うんです。
同じように、学校という制度についていろいろとお話してきましたけど、私は学校というのは、子どもたちが自分たちの学びを発見する場なんだと思うんです。しかし残念ながら、今の多くの学校は、「子どもたちに知識を与え、子どもたちにいかに上手に生きるか、うまく生きるか、いかに試験を乗り切るか。そして、人生の荒波を避けて楽に生きるか、努力を最小にし成果を最大にするか」と、まるで本当に三流のビジネスマンのように、子どもたちを育てる場になっているのではないか。それを教育だと思っているのではないか。みんなが根本的なことで誤解しているんではないか。そんなふうに、私はつい考えてしまいます。
もっともっと、子どもたちに自由を与えたい。子どもたちをほったらかしてやりたい。自由放任という言い方が、最近は悪い意味でも使われるようですが、あまりにも子どもたちの自分たち自身の空間、遊びの空間、その遊びというのは、いわゆる遊びだけじゃなくて、機械なんかで言う道具の遊びでもいいんですが、そちらの意味の方がいいかもしれません。ギシギシでない、つまり緩みがある。それは遊びがあるという言い方をよくしますけれど、そういうふうに子どもたちが自らの生き方を発見する。そういう緩みのある環境の中で、子どもたちを伸ばしてやりたい、と心から願った次第です。
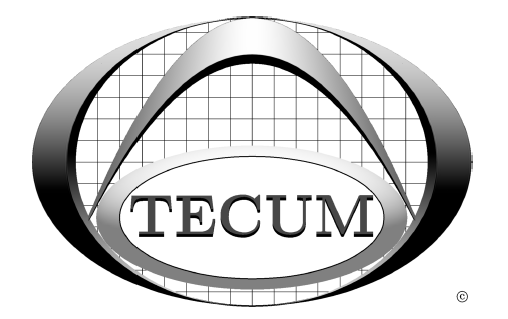
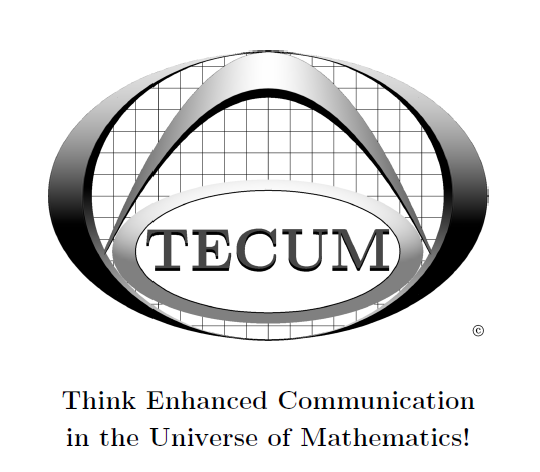

コメント
拝読していて,ちょっと胸が熱くなってしまいました。
全くおっしゃる通りです。人間の本来の素晴らしさが,ここには語られていると感じました。先生のように語ってくださる方がいるということは,まだまだ人間には希望があるということです。どうか若い方々に先生の尊い言葉が届きますように・・・