*** コメント入力欄が文章の最後にあります。ぜひご感想を! ***
最近私の知らない若い方からのメッセージをいただきました。それが大きなきっかけになりましたけれども、私が大変不遜にもお教えした昔の教え子の方から、すごく嬉しいメッセージをいただき、私自身も数学を教えるということに関しては、「普通の人とちょっと違ったスタンスをずっと持つこと」が自分にとって大切なことだと思っていただけに、大変嬉しく思い、大きなエネルギーを得て、今日のこの話に向かっています。
私がちょっと普通の数学の教師と違う立場で数学に向かってきたというのは、どうしても数学には技術的な側面があり、その技術的な側面についての知識を確実に伝えるということに力点を置いてしまう教員が多いと思うのですが、私は、どんな難しい話題であっても、その話題の技術性の中に私の講義を盛り込むではなくて、その技術をちょっと離れてみると、何が面白いんだろうというような、そういうタッチで、数学に携わってきました。様々なレベルの数学を教えてきましたけれども、一番低学年として、私が最初にあるいは大衆的にというか、多くの人に教えたのは中学校の段階の数学でありました。やがて、高等学校あるいは大学入試のレベルの数学を教えることが中心になりましたが、一方で大学での講義も行っておりました。大学では、私は数学をちょっとはたから見るという立場で、講義を組み立てることが多かったんですね。
それは大学の数学で言うと、例えば複素関数論であるとか、あるいは多様体論であるとか、集合と位相であるとか、線型代数であるとか、解析学であるとか、そういう細かいことを言いますと、きりがないくらいたくさんあります。でも私はそういうのを勉強する、あるいは勉強してもらうときに、そういう理論の「数学的な核心」と言われるもの、「その核心を別の言葉で語ると、これは何を言っていることになるのか」ということを、いつも中心に置いてきたように思います。というか、技術的な側面、例えばルベーグ積分っていうと、それに関する定理みたいなものがいっぱいある。その定理をいちいち証明していくというのはかったるい作業でありまして、そのかったるい作業をやるのは学生諸君1人1人で構わない。そういう本があるもんだから、その本を読んで勉強してほしい。でも、なぜルベーグ積分を勉強しなければいけないか。そういうモチベーションに相当するもの。それを伝えたいと思っていました。
大学入試においてもそうですね。過去に出たいろんな入試問題を一生懸命勉強するという人がいるんですけど、過去に出た入試問題は私から見れば99.9%はカスなんですね。他人のアイディアをパクッてちょっと変えただけのものですから、数学的な精神、スピリット、これはフランス語でエスプリと言った方がいいかと思いますが、その数学的なエスプリを感じさせるものっていうのは、例外的な存在でしかない。そうすると、そういう大学入試問題の練習問題をやるということは、私にとっても苦痛だし、それを強いている諸君にとっても苦痛だと私は思ったんですね。ですから、例えば一つの問題を取り上げて、その問題の中にどういう数学的なエスプリ、数学的なエッセンスが含まれているか、そのことがわかりさえすればあとは自分でできるでしょう。
でも、例えば何でもそうですけど、その事柄の本質っていうものは、やはり先生あるいは先達と言われる人から、一言教えてもらうだけでずいぶん違って見えてくるものですよね。私はできたらそういうのを伝えたいと思いました。中学校の数学から大学院のレベルの数学まで、数学といってもいろんな分野があるわけですけれど、そしていろいろなレベルの問題があるんですが、私はそれぞれのレベルに、中学生には中学生の、高校生には高校生の、学生には学生の、そして大学院生には大学院生の数学的なエスプリ、それがとても大切で、そのことに力点を置いてやろうとずっと思ってきました。私が書く本も、それこそ本当にレベルからすれば、これだけバラエティーに富んだ本を書いた人は世の中にいないんじゃないかと思うくらいたくさんいろいろと挑戦しました。分厚い本から薄い本、いろいろでありますけれども、いつも考えてきたのが「そのエスプリをいかに凝縮して上手に伝えるか。」その上手に伝えるかっていうのは、それが伝わりさえすれば、後はもう1人1人の読者が、あるいは1人1人の受講生が、あるいは1人1人の学生が独自で自分で道を切り開いていくはずだ。そういうふうに思っていたからです。
そんなことを思っていただけに、昔の学生だった人から、私はろくな教育をしてこなかったと思うんですけれど、やはり数学科を卒業したっていうことを海外に留学して改めて思い出す。その際に、私の記憶がどれほどあったか極めて不鮮明でありますけれども、応用数理の分野に進んだ方だと思いますけれども、私は純粋数学と言われるものを教えるときでも、常にそれの応用というのを頭の隅に、あるいは心の片隅に置いておりました。純粋数学には純粋数学としての高尚さ、そういう高尚な深淵さの魅力がありますけれども、一方で応用数学には、純粋数学にない独特のダイナミックな楽しさというのがあるわけです。そして、私が思う大雑把な数字ですけれども、純粋数学を勉強した人のおそらく99%の人は、社会に出てから応用数理の分野と格闘する。たった1%の人くらいが純粋数学の世界に残るということなんですが、実は「純粋数学を勉強していることが応用数理の勉強に最も役立つ」というのが私自身の持論で、なぜかというと、そこにおいて本当に数学のエスプリ、高尚な人間精神に出会う。そういう誇らしさ、そういうものを感ずることができるからだと思うんですね。
しかし、そういうことを感じて育った人は、それが応用数理の世界に応用される時にどれほど華やかに鮮やかに本当に色彩豊かな世界が急に開けるか、そういうのを実感されることだと思うんです。私は応用数理のそのような鮮やかな展開、それも私も決して嫌いな方ではありませんから、そういうものも頭の中に片隅に置きながら、やっておりました。技術的な話になると少し難しくなってしまうんですが、「有限要素法」という言葉が皆さんの投稿の中にありました。Finite Element Methodというんですけども、昔はこれが多変数の表現で、偏微分方程式と言われるもので、それに関して能率的に問題を解決するための本当に唯一の方法と言っても良いようなものでありました。有限要素法というとちょっとあまりにも専門的すぎるっていうか、もう今となっては少し古典的な話になりますので、さらに古い「差分法」という言葉を紹介しようかと思います。微分というのは「極限値を取る」、「限りなく近づく」というような文学的な表現で表現される世界でありますね。しかし、コンピュータを使って「限りなく」というようなロジックを実装することは非常に難しいわけです。ですから、コンピュータの世界では、これはコンピュータに限らず、理論的な物理学の世界であっても、しばしばある種の最小単位というものを、物理の人たちは量子 quantum(クオンタム)っていう言い方をしますけども、連続的なものを量子化して取り扱う。よくあるわけです。これは今日でも極めてポピュラーな話です。コンピュータで微分方程式のようなものを勉強する、あるいは研究するということになりますと、「極限を取る」というわけにはなかなかいきませんので、普通、微分で言えば、$\frac{yの無限小変位}{xの無限小変位}$、$\frac{無限小}{無限小}$というような分数にあたるもの、それを極限的に考える。分数で考えると極限取って$\frac{0}{0}$になる。それはただの矛盾ということになるんですが、そこは数学の非常に巧みなところで、そういう矛盾に陥ることなしに、そのような概念を取り扱うことができる。これが大学以上で一般に学ぶ、微分積分学と言われるものの基本なんですね。
ところが、その無限小というのを素朴に理解すると、具合が悪いことになる。そこで、いろいろなテクニックが、理論的な装置が用意されているわけです。それは置いておいて、コンピュータは無限小を理解できるかっていうと、できないわけですね。いくらコンピュータであっても、無限小は理解できない。でも、無限小に近いもの、つまり$0.1$とか$0.01$とか$0.0000001$、口で言っていくと大変ですから、例えば$10^{-10}$というような場合、小数点以下$0$がずっと続いていてやっと$1$が出てくるっていう数ですから、数学的に考えると、もう$0$とほとんど区別がつかないと言ってもいいものでありますね。でもそれでも有限の値でありますから、それをあたかも無限小のように扱えば、微分とかという数学でしか理解できないと思われていた概念でも、コンピュータを使って、擬似的に実装することができるわけです。
微分法というのが生まれて間もない頃、その極限という概念さえ無い時代、皆さん驚くべきことだと思いますが、ニュートンやフェルマーが最初に微分法を考えたときに、極限という概念を持っていたかというと、全く持っていなかった。よく大学の同僚で「最近の学生は極限概念もわからないで微分の計算をしてる」とか、「微分の定義も知らずに、微分をやってわかった気になってる。嘆かわしい風潮だ」っていう人がいるんですが、私に言わせれば「ちょっと待ってくれ。実は、私達の尊敬する微積分を最初に作り出した人々、ニュートンやフェルマーが、極限の概念なんか持っていたか、あるいは微分の概念を持っていたかというと、持っていなかったというのが正しい」。ですから、理論的なアプローチこそが全てだというふうに数学の先生は言いたくなるんですが、理論的なアプローチとは異なる、理論的なアプローチの生まれる前のアプローチといいましょうか、発見のためのアプローチ、そういうものは、数学では常に存在してきました。
応用数理の話に戻りますが、コンピューターで微分と同じようなことをやろうとすると、微分のモデルを有限のモデルで考え、例えば$\frac{\Delta y}{\Delta x}$というふうに分数で表現されます。それは決して単なる分数ではなくて極限をとる出発点になっているわけですが、その$\Delta x, \Delta y$は限りなく小さくなるっていうところに微分の面白さがあるわけです。$\Delta x^{-10}$に対応する$\Delta y^{-10}$オーダーのものだとしますね。最近のコンピュータだともっと小さくレベルまで、小さなオーダーをやることができて、$\Delta x^{-20}$オーダー、$\Delta x^{-30}$オーダー、そういうものも考えたんですよ。そういうふうに考えたときに、$\frac{\Delta y}{\Delta x}$はどんなに小さいと言っても所詮有限量で、有限量であったとしても、それが極めて小さな値になっていくと、あたかも無限小のような振る舞いをするのではないか。これは微分学の最初のアイディアでありました。ニュートンにしても、あるいはライプニッツなんかは極端に自分の方法を理論的に言葉でもって正当化する、そういうのが得意な人でありましたから、「無限小三角形」というような言い方をして、まさに極限を取るプロセスを、無限小三角形を構想するという形で、議論を進めております。実際のところは無限小を考えることができないわけですから、無限小三角形を考えていたということは、実は極めて小さな三角形を考え、こんにちの私達の言葉で言えば、$10^{-10}$とか$10^{-30}$とかそういうものを考えていたということ。
そして、昔はそのようなものは空想の世界で想像することができるだけ、あるいはいくつかの具体的な例で計算することができるだけでありますけれども、最近はコンピュータを使うことによって、人間だったならば、果てしなく時間のかかるようなことができるようになってきて、それが差分法とか有限要素法というふうに言われるもので、業界用語 jargon になりますが「メッシュ mesh」って言うんですね、「網目」。空間あるいは平面に小さな網目を考えて、その網目をどんどんどんどん小さくしていく。網目を小さくすることによって、言ってみれば微分に相当するものを隣同士の差でもって近似的に考えようということ。これをするわけです。こういう実用的な手法は、コンピュータの発明によって初めて可能になったわけでありまして、そのような基本的な理論を用いて、アメリカのNASAは、まさにボイジャー計画のような壮大なエンジニアリングの世界まで開拓したわけで、その大成功はこんにちは至るまで、本当に大きな伝説になっている。最近打ち上げられる様々なものに新しい技術が実装されていますけど、ボイジャー計画のようなものすごく果てしないアイディアに匹敵するものは、今はかえってないんじゃないかと私は思うくらい、素晴らしいものでありました。
そのような素晴らしい技術が、数理物理学の応用としてできるということは、コンピュータを使って人間が行うような、いわば非常に高尚な概念を数字的に近似する方法があるということなんですね。応用数理というのは、純粋数学があって、そして応用数学があるっていうふうに考えがちなんですが、本当の純粋数学の議論ができていると、それを応用するのは非常に簡単である。ちょっとしたアイディアのある人であれば、それを巧みに応用することができる。応用数理には応用数理特有の工夫の面白さというのがあるんですね。
こういうよもやま話では、数学の具体的な話をするということはとても難しいことですので、今日は「有限要素法」という素晴らしい20世紀を牽引したメソッドと言えると思いますが、その最初の出発点に、「微分を差分で近似する」。「差分」というのは、わかりやすく言えば、高等学校の勉強で言うと「階差数列」ですね。階差数列を取ることによって微分の代わりにするという考え方、本当はもうちょっと高級で、$y$で定められる数列の階差数列と$x$で定められる数列の階差数列を考える。$x$の階差数列というのは、いわゆる$\Delta x$というわけですから、$x$の毎回毎回の増分ということで単純ですね。$y$の方の差分も、$y$の隣の値と$y$の現在の値ということで、比較的簡単だと思うんですが、1階の微分方程式つまり第1次微分係数であるならば単純ですけど、第2階の微分係数とするとどういうふうにすべきか。さらに偏微分方程式としたとき、つまり変数が平面に広がっているような場合には、ふたつ偏導関数というのが存在する、$x$方向の偏導関数、$y$方向の偏導関数、そして$x$と$y$、それぞれの方向の偏導関数。2階の微分というだけでも3通りある。一般に$n$階の微分ということになると、ものすごくバリエーションが多いわけです。そういう様々なバリエーションの中で、いろいろな差分のモデルがある。そして極めて面白いことに、どのような差分モデルでやっても同じ解に行きつくと私達は期待するのですが、応用数学の世界だと誠に不思議なことに、この差分モデルを使うとうまくいき、この差分モデルを使うと全然うまくいかない。計算の精度をよりよくする、向上させれば向上させるほど、真の解とは縁もゆかりもないものに発散していってしまう。そういう恐ろしい世界があるわけです。理論的には、細かくすれば細かくするほどいいになるに決まっていると思うのですが、細かくすれば細かくするほどダメになってしまう。そういう難しい問題が潜んでいるということを、発見した応用数理学者がいまして、本当に偉大な発見だと思いますけれども、細かく計算しさえすれば良いわけではないということですね。
私達はその問題に接近するのに、ある特定の方法しかない。こういうことも20世紀になると発見されるわけですね。ちょっと楽しいと思いませんか。私自身は、そういうときに、「こういう技術がある。こういう技術がある。こういう技術がある」と、技術を一覧表にして、うまくいくものもうまくいかないものも片っ端から調べる、というようなことは、研究者がやるようなことだと皆さん思うかもしれませんが、本当の研究者はその中で「絶対ダメなものというもの、そして必ずうまくいきそうである」、これを独特の臭覚で見分けることができる。そういう優れた人々なんですね。研究者が片っ端から調べているというのは、これは庶民の抱く研究者に対する誤解の一つでありまして、研究者は独特の臭覚で、良い問題にしか惹かれないということです。つまらない問題、やってダメな問題、それは最初から切り捨てる。
そういう臭覚は何に由来するか。私は言わせれば、それは「純粋数学のエスプリ」といったものです。純粋数学を勉強するときでさえ、あまり勉強に成功していない人が少なくない。純粋数学の中から本当に大切なエスプリを感じ取れる人は、実際は少ないわけです。ですからあとの人は「銅鉄主義」というふうに学問の世界で言われる、「人が銅で成功したものを鉄でやってみる。」こういう研究をする人は数多くいるんですが、私が大学に入ったときに、全く右も左もわからない大学生に対して、自然科学系の先生、数学の先生だったかもしれませんが、その先生の授業で、最初に「研究者っていうのは、何をやっても自由だと世間では思われている。でも最低限君達は銅鉄主義になってはいけない。」そういう訓示を垂れてくれました。私にとっては何を言っているのかよくわからないことでありましたが、実際自分も研究者の端くれみたいになると、銅鉄主義ばっかりと言ってもいいくらいなんですね。
でも、真に偉大な研究っていうのがある。その真に偉大な研究というのが、純粋数学にも応用数学にもあるんだっていうことを、今日は皆さんにお伝えしたいと思いました。いずれにしても大切なのはエスプリで、それはちょうど音楽や絵と同じなんですね。演奏が上手だということが、今の日本ではしきりと持て囃されます。でも、音楽では演奏が大切だということではなく、その楽譜の中に、どんな作曲家のメッセージを読み取るか、そこが勝負なんだと思いますが、楽譜を読めない演奏家が増えてきているということ。私は実際の演奏家からその話を伺ったときにとても悲しく思いましたが、それは学問をやる人、数学者の数、物理学者の数、それは爆発的に増えている。でも、学問のエスプリに触れることのできる人は、ほんの一握りであるということと似ているなというふうに思いました。今日は皆さんに勇気づけられて、ちょっと調子に乗って、数学や応用数理の話をしてしまいました。全く訳がわかんないと思った方もいらっしゃると思うんですが、数学でも、数学者のとても大切にしている数学的精神というのがあるんだと。厳密な論証とか正しい計算とか、そういうものはどうでもいいと思っている数学者がいるんだ、ということを理解していただけたらこの上なく幸せです。
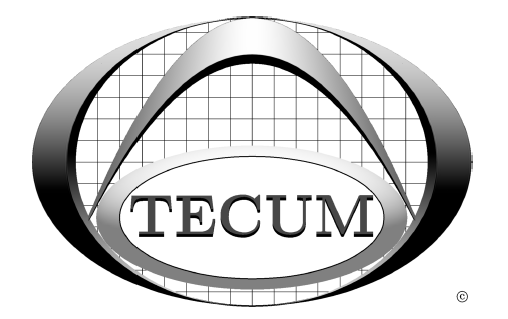
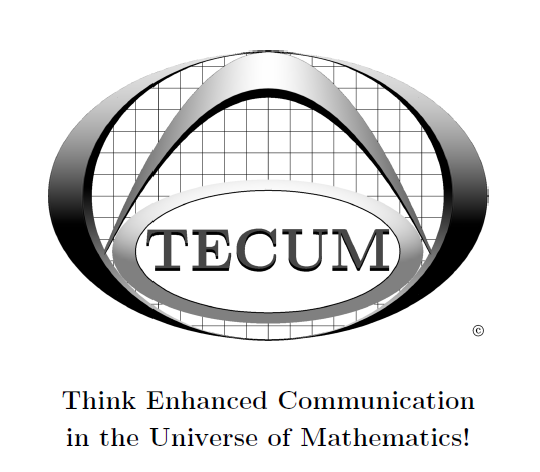

コメント