*** コメント入力欄が文章の最後にあります。ぜひご感想を! ***
今回は、ちょっと毛色の変わったお話をしたいと思います。それは、キリスト教についてということです。宗教の問題について具体的に話すと、厄介な議論に巻き込まれます。キリスト教の前にはユダヤ教があり、キリスト教の後にはイスラム教があり、そしてそれぞれの宗教の中で、非常に厳しい分派闘争が続いているわけですね。キリスト教に関しては日本ではプロテスタントとカトリックという分類だけが有名でありますが、プロテスタントという近世に生まれた合理主義的なキリスト教の他に、むしろ神秘主義的な傾向を持つキリスト教とか、あるいは土俗的な文化と結合したより原始的な匂いを強く持つキリスト教もありますし、さらに、近代において生まれた原理主義的な、とでも言っていいんでしょうか、キリストの基本とする精神に立ち返ろうという、いわば12世紀に起こったようなキリスト教内部での反宗教改革的な動き、つまりキリスト教の原点に戻るっていう運動ですね。修道院運動なんていうのはその典型でありますが、それに相当する運動を日常生活で実践している宗派もあります。
ですから、キリスト教と一言で言っても、宗教として一つのくくりに入れるということがそもそも適切でない。どの教義を信ずるか。つまり聖書として何を認めるかというところでも、歴史的には大きな論争があったわけでありまして、今、私たちがこんにち持っている、例えば新約聖書を構成している四福音書っていうのがありますが、その四福音書以外にも、外伝って言われる様々なイエス・キリストについての生涯の物語を書いたものがあるんですね。それが、しかし真の神の言葉ではないというふうに、いろんな神学的な研究の結果決まって、今の四福音書っていう形になっています。多くの人にとっては、聖書っていうとその四福音書のことばかり力点が置かれているかと思いますが、新約聖書の中にもそういうくくりでくることが非常に難しい神秘主義的な香りを持つ“黙示録”というものもあり、様々な芸術家の芸術的創造のイマジネーションのもとにもなってきました。
聖書について語るだけでも、そのようにいろいろと多面的な要素が当然あるわけです。当然のことながら聖書の教えをイエス・キリストという一人の人物と結びつけ、その人物が神の子であり、聖霊とともにあって、天の神と三者で一つの神を創っている“三位一体”というキリスト教の基本教義がありますけれども、その基本教義の大元となるのは神、これはわかりやすい存在であるわけですね。ユダヤ教のとき以来「神は唯一である」と、一神教と非常に重視されてきました。キリスト教のときから、神しばしば父、と呼ばれ、子キリスト、イエス・キリストですね。それは、神が地の民を救うために使わした自らの息子であるという教えであります。キリスト自身が自分は天の父なる子供であると、そういうふうに言っていることから、聖書を信ずる人はキリストの言葉を信ずるということになるわけですね。
キリストの言葉というのは、実に深遠で、哲学的で、そして根源的なんですね。その厳根源性というのは、ある意味で、私のような本当に平凡な日々を送る人間にとっても、数学的に見ると非常に心を打つものがあるわけです。例えば、「金持ちが天国の門に入るのは、ラクダが針の穴を通るより難しい。」この例えって一体何なんでしょうね。単に不可能だと言ってくれればわかりやすい話だと思うのですが、不可能だと言わないところが面白いところだと思うんです。ラクダという巨大な動物が針の穴を通る。これは普通には絶対できないことですね。常識的にはできない。できるはずがない。でも、それも実は神の技を持ってすれば不可能ではないっていうことを示唆しているわけです。そして、しかし、金持ちがつまりこの世の中で栄華を極めた人間が、その栄華を人に与えることなく天国に召されることはより困難であると。神の深い慈愛をもってしてもそこはさすがにやり難いということなんだと思うんですけれど。ある意味では、人によっては文学的な表現あるいは叙情的な表現というふうに言うかもしれませんが、私から見ると、すごく数学的な表現だと思うんです。ラクダが針の穴を通るということを、ラクダの断面積と針の開口の面積、面積の大小関係によってその可能性を論ずることができるかというと、もしラクダがふにゃふにゃしたものであるならば、皆さんの中にはトポロジーって言葉を知っている人もいらっしゃると思うんですが、ラクダにトポロジカルな変換を施してやるならば、針の穴を通すような変換を強引に行う。そのときラクダはかなり苦しいかと思いますが、あり得ないことではない。だからその聖書の言葉の中に、すごく私は惹かれるものはあるんですね。それは決してできないとかできるとかって言っているんではないんですね。
ある場面では、カエサル、シーザーですが、ローマの皇帝の顔を彫った金貨を流通したローマの支配地で、当時のエルサレムなんかそういうところで、そのカエサルの金貨を使って納税する。あるいは徴税する。そういう仕事に従事している人は、カエサルに仕えている、ローマ皇帝に仕えていることなり、神の子としてふさわしくないのではないかという神学論争をふっかけられたときに、イエス・キリストはどう答えたかと。普通だったら、「そうだ、その通りだ。カエサルの権威なんかひっくり返せ。ローマ皇帝の持っている政治的な権威で、それは虚構である。人民が立ち上がればいい。いっぺんに吹き飛ぶ。」そういうふうに決起を呼びかけてもおかしくなかったと思うんですね。政治的な権威と権力っていうのは、それを支配する人々が従順であるということ、人々を平定することができるという一つのフィクションの上に成り立っているわけですから、人々が本当に抵抗したら、あっけなく崩壊するわけです。どんなに大きな権力といっても、人々が反乱を起こしたときは、本当にひとたまりもない。それは最近でいえば、プリゴジンの乱というのに青ざめたプーチンを見ても明らかでありまして、どんな権力者といえども、人民が静かに収まっているということが、彼らの安心の大前提なわけです。ですから、そのときイエス・キリストが反乱を呼びかけてもおかしくないと思うんです。でも、その反乱を起こすとか起こさないとかという議論と同じ土台に立ってない。イエス・キリストが言ったのは、「カエサルものはカエサルに。神様のものは神様に。」そういうふうに言った。これは、二つは価値観が全く違う。カエサルのもの、それはカエサルのロジックの世界の中で生きる人はそれを大切にしなさいと。だけど、カエサルの価値観と違う価値観の中で生きる人は、神様の世界に来なさい。こういうふうに完全にロジックをひっくり返すわけですね。何か数学的に見て、ちょっと素晴らしくないですか。
キリストの新約聖書に見られる言動のいくつかに、こういう聡明さ、果てしない聡明さが宿っていることは明らかなんですが、キリスト教が世界宗教として、ユダヤの一部の人々が信ずる地方宗教ではなく、世界宗教としての地位を確固としたものとしたのは、私はおそらく、そのキリストの生きた証というだけではなくて、もう一つ、やっぱりキリスト教徒を弾圧した側のローマ兵士、兵士といっても兵卒ではなくて将軍であったと思いますが、パウロという人がいます。英語のポールっていう名前、フランス人もパウルといいますね。アメリカ人でも。パウロというのはキリストの正式の弟子というよりは、キリスト教徒を弾圧する側にいたローマ軍の将軍だったわけです。そのパウロがキリスト教徒を弾圧した最中に落馬して、そのときに突然天の啓示を受ける。啓示っていうのは、英語ではrevelation、ラテン語ではrevelatioと言うんですが、啓示を受けて、天啓を受けて、突然回心する。突然回心したパウロが敬虔なキリストの弟子として、地中海各地のそれぞれの地方のキリスト教徒に対して送った書簡というのがたくさん残っているんです。その書簡が素晴らしいんですね。よく結婚式でも音読する、神父さんが読まれるとかパウロの『コリント人への前の手紙』、『コリント前書』と言われるフレーズがもっと有名なものですね。私は“パウロ革命”っていう言葉をあえて使いたいんですが、キリスト教の中にある教えをすごくわかりやすい言葉で凝縮して、表現し直した。それまでの四福音書っていうのは、ある意味で史実に忠実に書いた福音書、それから非常に先進性豊かに、思想性豊かにというか哲学的に深く書いた福音書もあるんですけど、パウロのように、「キリスト教が伝えようとしたのは、愛の教えだ」っていうことを鮮明に打ち出して、すごくわかりやすく、しかも厳しい言葉にまとめたのはパウロなんだと思うんです。私はそれを“パウロ革命”っていうふうに言っているわけですが、キリスト教が、ユダヤ地方の、あるいはイスラエルの地方の一宗教であることを超えて、世界宗教として巨大化するときにパールが果たした役割っていうのがすごく大きい。私はパウロっていう個人を崇拝せよと言っているんではなくて、パウロの言葉が素晴らしい。パウロの言葉は、パウロが語っているというよりは、パウルを通じて神が語っているという理解が、キリスト教の公会議って言われる大きな議会みたいなもんですね。西暦、私は正確に年号を覚えていませんけど、7世紀くらいに開かれた公会議で決められたんではないかと思いますが、それは、パウロ個人の言葉ではなくて、パウロを通して語られた神の言葉であるということです。
この言葉の持っている普遍性っていうのは、他の宗教にも多く見られるわけでありまして、決してキリスト教だけの専有物ではないですね。宗教間の対話っていうことが、20世紀になって以来しきりと語られるようになり、そして21世紀に向かって宗教が文明の衝突の原因になるのではなく、文明の共存、文明の融和の象徴となる方向で理解が相互の理解が進んでいってほしいと心から願っておりますが、実際そうであった時代もあるわけで、今のように対立しているのは全ての時代で一貫しているわけではないと思うんですね。ですから、その宗教間の融和が何よりも大切だと思うんですが、その融和を実現する上で前提的な知識として必要なのは、相互の理解、相互の主張、相互の信仰を支えている根拠、それを理解し合うことだと思うんです。私は、残念ながらユダヤ教やイスラム教について、こういう話をするだけの基礎教養がないので、いつかイスラム教やユダヤ教についてお話したいと思っています。また中国は仏教で、中国や日本は仏教や儒教の国だというふうに思っている人がいますが、中国人の大多数は道教っていう思想でありました。そういう仏教、儒教、道教という文化についても、わかる範囲でお話していきたいと思いますが、やはりそのためには何よりも必要なのは、哲学的な厳密な理解と歴史的な文化に対する包容力のある理解だと思うんですね。私はいずれも不足してる人間ですので、私の生きている間に達成できるかどうか、甚だ怪しいことでありますが、これからもまだ生きていくだろう皆さんにはぜひ、宗教間の対立を「調和をもたらす。融和をもたらす」そのためにも、いろいろな宗教について知識を深めていってほしいと願っております。
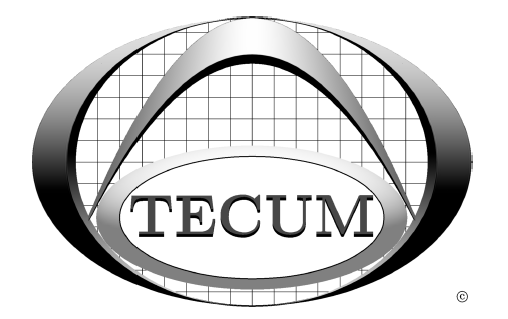
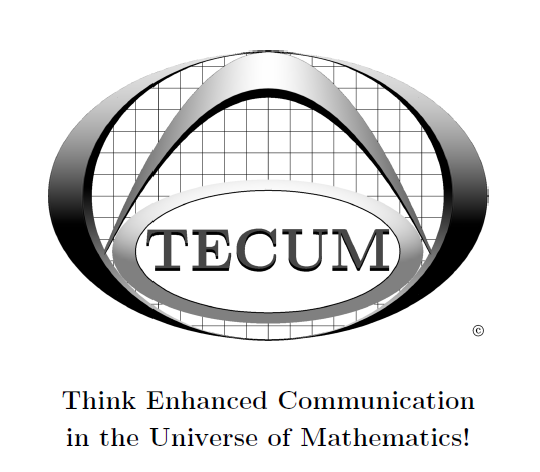

コメント