*** コメント入力欄が文章の最後にあります。ぜひご感想を! ***
今回は、私達の生活の中に深く根付いている慣習について考えてみましょう。例えば、生まれたとき、生まれて間もない七五三という風習が日本の各地に残っていて、結構熱心に行われていますね。このような形式が一般に流行ったのは、まだ百数十年の伝統しかないんだと思いますが、今ではすっかり決まりごとのように行われています。それをやらない人が、いわば風習に反する、あるいは伝統に反するというふうに強く言わんばかりの人もいます。普通は神社に行くわけですが、私達日本人の中で神道を心のよりどころに生きている人、あるいは神道の宗教的な教義について理解している人、あるいは理解とは言わなくてもほんのちょっとでも知っている人は、どのくらいいるでしょうね。神道の神棚にまつられているものは、一体実態としては何であるかということさえ知らないのではないでしょうか。
かつて、私の若い時代でありますが、“天照大神”というのを「てんしょうだいじん」と呼んで笑われた話がありますが、もうその時代から私達は、漢語を日本語に割り当てるというふうにして日本の文字を作った古事記とか日本書紀の時代と違って、漢語を日本語として読むことができるようになっているわけですから、「てんしょうだいじん」と読んだのも決して不自然ではないわけでありますけれども、昔の年取った人たちから見れば、「最近の若いやつはなんと教養がないんだ」というふうに思ったんでしょう。しかし、漢字の言葉を日本語で読むということの方が、本当は強引なことでありまして、「てんしょうだいじん」と読んだ、馬鹿にされた当時の若者を私は擁護してやりたい気持ちがあります。彼は彼なりに、あるいは彼女は彼女なりに、首尾一貫した文化の中に生きていたということです。それに対して、漢字を日本語読みするということの中に、日本の文字さえ持たなかった私達の文化を、中国から先進文化として取り入れた人たちの苦労を思い出して考えることは良いことだと思いますが、正解はこれだというふうに言うのはちゃんちゃらおかしいと思います。
つまり、私達は例えば七五三という文化、伝統というふうに思っていますけど、その伝統の起源を考えると諸説紛紛、大したものではありませんから、あんまり古くまでさかのぼることはきっとできないですね。ですから、子供が7歳とか5歳とか3歳とか、生きてきたらそれで一段落というふうに思い、神に感謝するということだと思いますが、日本人の中で神道に帰依していない人間が神に感謝するということはどういうことか。それは宗教的なものというよりは、いわば地域共同体、親戚とか一族とか、そういう地域共同体の中での慣習が続いていたに過ぎない。地域共同体っていうのの起源を遡れば、やはり明治時期くらいまでしか遡ることができない。江戸時代になりますと、もちろんそこまで遡れば、農民の間での団結とか、あるいは侍の中での団結とか、そういうお家の団結というのはあったと思いますけれども、脈々とそれが続いている伝統だっていうふうに言うことは、ちょっとおかしいという気がいたします。
私達は、文化的な伝統っていうのは一貫して持ってないにもかかわらず、ある段階から始まった文化に対して、妙にそれを正統的なものっていうふうにして崇める傾向がある。これこそ、明治維新政府が進めた文化政策なんだと私は思っているんです。江戸時代の庶民はもう少ししたたかであったと思いますが、明治時代に「近代化」されたという、近代化はかっこ付きの近代化でありますが、その日本人が本当にきちっとした理由もわからず、周りに合わせていたということ。周りに合わせることによって、神道を日本の宗教の中で大きな存在として確立したということなんだと思います。一方日本の中には、仏様を信ずるという根強い庶民的な信仰がずっと残っていて、今でもほとんどお葬式は仏式でやる、仏教でやるというのが一般的ではないでしょうか。仏教を信じているというわけではないと思うんです。というより仏教の教えというのは、もう宗派によってえらくバラエティーに富んでいて、それのきちっとした典拠を勉強しているっていうのはお坊さんでも例外的な少数になりますからは、本当に意味がないといえば意味がない。日本人は宗教心は非常に深いのですが、ヨーロッパの人のように宗教を自分の生き方と重ねてそれを生きるっていうことはあまりない。つまり、日本人は生きている間だけ人間として恥ずかしくない生き方をするという程度の宗教心ですね。よく揶揄されることですが、生まれたときは七五三、神式、神道ですね。結婚するときにはキリスト教、キリスト教式の結婚式。そして死ぬときは仏式。これが日本の一般的な家庭で行われているものではないかと思いますが、これをもって日本人の宗教はデタラメだと言うのは、私はちょっと違うと思います。
日本人には宗教心はあるのですが、宗教について無知であるということですね。よく言えば、日本人は言ってみれば原始的な宗教観の中に未だに生きている、というのが一番正しいんだと思います。八百万(やおよろず)の神というような類の神を畏れる心というのはどっかに持っていて、しかし具体的な神々の教えに日々の生活を合わせるということはしない。ある意味で、非常に自分に都合の良い生き方をしているようでいて、宗教心を持っていませんから、やっぱり死ぬときに非常にみんなバタバタするんですね。生きているうちが花だよというような、人々の間に交わされる言葉、そして私の友だちと会うとやはりPPKっていうのがもう流行り言葉というか、みんなの同意する言葉で、ピンピンコロリ、ずっと元気でいて突然ある日亡くなる、とこれが一番生き方として理想だとこういうような言い方をする。これは結局、生きているということを大事にしながらも、結局死んでいくということを受け入れざるを得なくなると、そのときにころりと死ぬ。そして一巻の終わり。そういう感じなんだと思うんですね。生きていることが死とどのように結びつくか、ということについて私達はあまり考えていない。
私自身がこういうことを考えるようになった最初のきっかけは、生まれて初めてヨーロッパ、イタリアの大寺に行ったときに、そのイタリアのお寺の地下室に行ったんですね。そしてその地下室でびっくりする光景を見ました。それは人間の骨、骸骨。頭部だけではなくていろんな部分の骨、それも全てきちっとというよりは乱雑に埋められている。埋められているところを、私達は見ることができるわけです。日本では、遺骨といっても火葬にしまいますから、ほとんどボロボロになってしまって原形をとどめていない。本当は原形をとどめているに違いないと思いますが、日本では、遺骨のままではそれを埋葬することができないということで、担当の係の人が砕いて持ってきて、骨壷というのに入れて埋葬する。そういうやり方をするのでしょう。言ってみれば、生前の姿っていうのがものすごく抽象化されて、違うものになるわけですね。そのことによって人々が、死はこういうものだっていうふうに受け入れているんではないでしょうか。ヨーロッパのお寺に行ったときに、私がショックを受けたのは、まさに人間が普通に生きているときの姿、それが肉や皮が剥げているために、いわゆるドクロになっている。そのドクロが、もう累々と積まれているんですね。どういうことかって言うと、そのドクロになるということと、生きているということが繋がっている。日本人のように、それを焼却して、砕いて、粉々にして、姿形を全く変えたものにする。そして素材を大事にする。それがまたよくわからないところですが、日本の文化ですね。これが続いているんですけど、結局そのことは何を意味しているかっていうと、ヨーロッパでは、生前と死後がやはり繋がっている。生きているということがやがてこういう形になるんだということ、それをいつでも見えるようにしているっていうことですね。今はさすがにそういう形の埋葬は例外的でありましょうが、当時人々が多く住んでいるところでは、そのようにする以外には埋葬の方法がなかったわけでありましょうし、生きている間、常に死ぬ明日のことを考えて今日を生きるということが、重大視されていたのでしょう。
私達は逆に、自分たちが明日死ぬということを考えずに、今日も生き、そして明日もそのように生きているであろう、昨日もそうであったし。そういうふうに生の世界から死の世界までダラダラと繋がっているというふうに思っている。そして、何か不条理なことに、そのダラダラと続いている日々がある日突然途切れてしまう。それが寿命だという言い方をしているんですけれど、本当はそこに連続性があるのか、あるいはそこに不連続性が、不連続であることは明らかですが、その不連続というのを全く関係ないものというふうに見て良いのかどうかということについて、もう少し深く考えてみる必要があるのではないでしょうか。つまり、生きていることということと死ぬことというのは、同等に重要な意味がある、と私は結論的にはそう思うわけです。死ぬということの意味を考えることなく、生きていることの意味を考えることはやはりできない、という感じでしょうか。このような言い方をすると、私が宗教教団でも結成しようと思っているんではないかと疑う人もいるかもしれませんが、私は霊感商法にはあまり興味がありませんが、人が自分の救いを求めて自分の現世の利益を犠牲にするという気持ち、これはある意味で宗教的な情緒の出発点なんだと思いますね。つまり、「生きていること」、これがやがて終わる。やがて終わるけれども、それはかりそめの終わりであって、実はその先が続くんだという感覚。それをできるだけ理知的に考えるということと宗教は深く結びついている。「死ぬということ」の意味を考えることのない人は、死ぬことは人生の終わりでしかありませんから、そのことを恐怖の対象としてしか捉えないということもあるかと思います。
最近の日本の状況を見ていると、死と向かい合うことを忘れた国民がどの方向に向かっていくのか。そして死を忘れた国民に育てられた若者がどういうふうに育っていくのか。少し暗たんたる気持ちになります。昔の言葉でありますが、「一秒一刻が、毎秒毎秒あるいは毎刻毎刻、一瞬一瞬、君を傷つけている。そして最後の一瞬が君の命を奪う」と有名な言葉があって、それは私が子供の頃英語で習った言葉でありますが、そういう常に死を意識するという生き方、それを私達はちょっと忘れているんではないか。COVID-19の大騒ぎでも、私はそれを感じておりました。
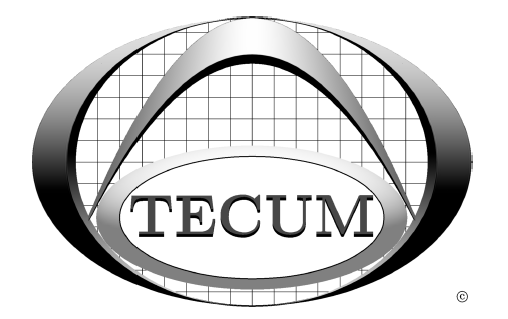
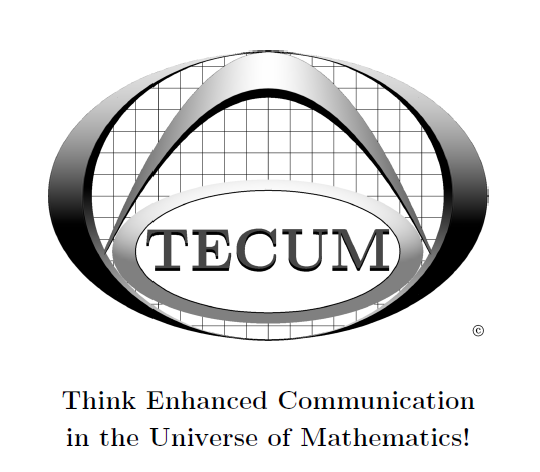

コメント