前回は、最近の広告宣伝が無条件に悪いことではないということが基調になって、いい加減な知識のもとに、あるいはひょっとすると正確な知識のもとに、つまらない余計な情報をときに人を誤解に導きかねない情報を、平気で発信している人が多くなったというような話をいたしました。それを受けて、では反対に、いわゆる「専門家」という人はどうかということについて、お話したいと思います。日本では、高等学校以下の先生のことを教員とか教諭と呼び、大学の先生のことは教授と呼ぶ。大学の教授だと突然立派な人になるというふうに思っている人がいるのですが、今の大学教授の総数というのは戦前の中学校の先生の数よりも多いくらいでありまして、よく言えば高等教育が普及しているという状況を物語っていますが、一方で国民全体の中で占める高度に知的な人々の割合というのがそんな簡単に増えたというふうに思う統計的な理由はあまりないわけですね。栄養が良くなることによって、精神的な成長、肉体的な成長が早くなるということはあるのかもしれませんけれど、頭脳が明晰なる、見識が広くなるというようなことが簡単に起こるとは思えない。そういう意味で、大学教授という名前がつく人、私もそういう仕事を長年やってきましたけれども、それを無条件に「知識人」、あるいは一昔前の言い方と「知識階級」、ロシア語のIntelligentienza(インテリゲンツア)っていう言葉が今日本で普及して「インテリ」というふうに言いますが、そういう知識階級あるいは知識階層って言われる人々がものすごく増えているわけですが。それが本当の意味で、昔の知識人が果たしていた役割を果たしているかというとかなり怪しいということ。これをちょっと少し深い観点から考えてみたいと思います。不快感深い観点っていうのは私が勝手に言っているだけで、ひょっとするともっと普通の人とちょっと違った観点という程度で、できればそれが皆さんの深い理解へと導くことができればっていうのは、私自身の願いに過ぎないかもしれません。言い換えれば、大学教授に代表されるようないわゆる「高度な知識を持った先端的な学問の知見を有する専門的知識人」ということですね。その人たちが、昔の知識階級に要求されていたようなことができるようになっているかというふうに、私の問題設定を立て替えてもいいと思います。21世紀の今にあって、「知識人とは一体何か」ということです。ある意味では、知識人というのは知識の専門家というふうに見ることができますね。多くの人はそう考えているのではないでしょうか。日本において、大学の先生が一般に大変尊敬していただけるということはありがたいことではある。学問を国民的に底辺から支えてくれている。そういう世論が存在するという意味ではありがたいことではあるけれども、一方で大学の教授というだけで、専門性あるいは知識あるいは広く見識に対して、無条件の信頼を寄せていることは本当に大丈夫なのか。そもそも知識の専門家というのはありうるのか。そして、知識の専門家があり得たとして、それがいわゆる「知恵を持った深い賢者として尊敬することに値する人なのか」というように、問題を広げていきたいと思っているのです。
教授というのは英語でProfessorと言います。Professorという言葉は、Profession職業っていう言葉と関係していて、教育を専門とする人のことをProfessorと言うわけで、日本では、先生っていう言葉に比べて教授という言葉が何か妙に重々しい響きを持っているようなのですが、フランス語ではProfesseurって言葉は、幼稚園の先生でもみんなProfesseurっていうわけで、本来は職業教育人あるいは専門的教育職、そういうふうに言った方が正しいと思うんですね。要するに、教育で食っているということです。かつて本当に深い学識を持った人のことはProfessorではなくて、今でもそうですが、Academician学術の人と呼んだわけです。academyという言葉は、もちろん有名な古代の哲学者プラトーンの開いた学校akademeiaに由来する非常に重要な言葉でありますけれども、その哲学に裏付けられた、あるいは最先端の自然科学的知見、当時は数学でありましたが、あるいは天文学でありましたが、そういう厳密な学問に深く根ざした哲学的な叡智を持った人、それをみんなが目指していたわけですね。そしてそういうことをたち成した人を、英語で言えばAcademicianといって尊敬してきた。Academicianというのはある意味では「王様のペット」というと言い過ぎですが、王様の自分の権威を高めるための装置として、王侯貴族の間にちょっとしたレクチャーをするという義務を負う学者集団ということで、特別の待遇を受けていたわけです。かつての絶対専制君主何かのもとにはacademyが組織され、今でも歴史に名前を残している立派な学者たちがそこで研究をしていた。
そういう時代から、やがて大学という制度が一般化してくるわけですね。元々大学っていうのは、12世紀くらいにはヨーロッパ諸国にはできていたわけでありますが、その大学で教えられたのは、法律とか医学とか哲学とか神学でありまして、数学のような学問というのは、そういう哲学とか法学とかってそういうのを勉強するための基礎学問、当時は英語にするとLiberal artsていうふうに今言いますが、日本では非常に大衆化した教養っていうふうに訳されていますが、liberalというのは自由ということですね。自由な諸芸ということで、諸もろもろの芸ということです。artsとは芸術っていう意味だというふうに日本ではまた独特のほ意味をそれに持たせていますが、本当はartsというのは、いわゆる日本の狭い意味での芸術だけではなくて、あらゆる意味でのその道のたち人たちが探求するようなものでありました。当然学問も含まれますし、音楽に関して言えば、音楽の楽器を作るための理論的な研究、和音の研究とか、その和音を出しやすくなる楽器の研究であるとか、そういったものもartsでありました。そういうartsの中から、皆さんよくご存知の例えばドイツなんかでは技術者、マイスターって言いますが、いろいろな職人さんたちのトップに立つような本当に職人技、日本で言えば宮大工のような世界ですね。そういう世界も開かれていたわけです。そういう手を動かして技を発揮する人たちもいれば、ひたすら頭脳によって叡智の世界を切り開くという人もいました。こんにちの私たちから見れば、形而上学的な思弁にふけっていたというふうに一括されてしまいそうな哲学的な議論を繰り返した人たちもいました。そして驚くことに、数学のような厳密な学問研究に耽っていた人もいたわけであります。そういう人々は、そういう深い学識をもとにして、その深い学識の専門領域とは違う領域についても、普通の人とは違う見識でもって迫っていたわけですね。だからこそ、王様に特別の待遇で処遇されていた。普通の一般貴族から見れば、「訳のわからんことをやっている人たちがなんでこんなに高い給料もらえてんだ。なんでたくさんの召使がつけてもらえているんだ。なんでいい暮らしができるんだ」と、僻みもあったと思います。しかしながら、多くの絶対君主は、そういうAcademicianを自分の周りに寄せて集めておくこと、そしてその人たちに訳のわからん講義だったと思いますが、それを聞くことを自分の権威を高めるための道具として、そのacademyに対して多額の予算を割いていたわけであります。そういう多額の予算をacademyに対して割く一つに「音楽家を養成する」っていうこともありまして、今のように音楽家が演奏家として生きていくという時代。それはいわゆるクラシック、英語でClassical Musicって言われる近代になってからもそうで、ほとんどの偉大な作曲家と言われる人たちも、実際の自分の音楽の演奏で食べているっていうことが多かったわけですね。作曲した楽譜はむしろ人に見せないで隠す、そういう音楽家も少なくなかった時代であります。要するに、それも宮廷あるいは王様の前で、立派な芸を披露する。そして王様の権威を高めるということ、それが重要な任務であったわけです。
しかし、そのことが王様の権威を高めることに繋がるというくらい深い学識を、彼らの専門的な学問的な研究を通して、あるいは芸術的な修練を通して示すことができたわけですね。その時代のAcademicianというのは、専門の世界で優秀だというだけでは当然生きていけないわけで、それは王様たちの前でその専門の世界を語ってみるところで、それはくだらないねって言われたらおしまいなわけですね。しかし、その専門家たちが集まる中で、その専門家たちがいろいろ話をする。その専門でないことも話をする。専門でないことを話をするときには、専門じゃない人も耳を傾けて理解できることであるわけです。そしてそこに、自分たちが考えもしないような深い思索があるということを知ると、その人たちは「この人は本当にすごい人だ」と思うわけですね。そしてその尊敬される人々が「いや、私なんかはこの人に比べれば本当に爪の垢みたいな存在に過ぎませんよ」というもっとすごい深い専門性を持った人のことを尊敬すると、その人がアカデミーのトップの人として処遇されてきたというわけです。
私たちが専門家をそのように大切にしてきたというのは、いわゆる市民革命が始まる前、まだ絶対王政というのが残る時代、市民革命が起こった時代にあっても、イギリスやフランスでは王様が追放されたり、あるいは王様の権利が制限されたり、そういうことありましたけれども、後進国ヨーロッパ特にドイツ地方なんかではまだ皇帝というのは大きな権威を持っていたわけですね。ロシア帝国なんていうのは大変なものであったわけです。しかしながらその市民革命を通じて、大学という制度が一般の市民に開放され、その大学において、神学とかあるいは宗教とか哲学とか法律とかということを研究するというだけではなく、数学とか物理、昔は物理という言葉ではなくて自然学といったわけですが、そういったものを数学を通して研究するっていう分野が次第に確立されてくる。その画期的な成果をまとめたのがニュートンでありまして、ケプラーという非常に不思議な天文学者、不思議な人物でありますね。天才的なひらめきと天才的な努力によって、驚くべき惑星の運行法則を発見したわけでありますが、そのケプラーが観測に基づいて確立した、あるいは提唱したって言った方がいいかもしれません。その惑星運動の仮説をアイザック・ニュートンはなんと万有引力という仮説、そして力学という法則、古典力学と私たちはよく言いますけれども、それはアインシュタイン以降の現代力学とだいぶ話が違うからでありまして、しかしながら私たちが普通に日常的に暮らしている世界においては十分精度よく当てはまる力学の世界ですね。その力学を用いて、太陽系の運航というのを、ケプラーが発見した法則を厳密に数学的に導くっていうことに成功したわけです。なんとも驚くべきことでありまして、当時の人々の中にはニュートンを称えて、神は言われた「God said “Let Newton be”」。これは非常に有名な言葉で、皆さんは「Let It Be」とか、そういう言葉でそういう英語をご存知だと思いますが、”Let Newton be”っていうのは、もし直訳するとすれば、ニュートンぞ存在せよ、ニュートンぞ在れかし、そういう言葉になると思いますね。ニュートンの学問的成果というのは、当時の人々をも本当に心底びっくりさせるような成果であったわけです。そのアイザック・ニュートンは、しかし自分の数学や自分の物理学というのは周りの人にきちっと理解してもらえるかどうか自信なかったんですね。と私は思うんです。というのも、ニュートンはものすごくたくさん原稿を書いているんですが、そのほとんどが発表されない原稿、よく手で書いたものということでマニュスクリプト、日本では写本と訳されることが多いんですが、別に写し取るということがニュートンの仕事だったんではない。ニュートンは紙にひたすら文字と数学の計算は、今から見ると信じられないほど面倒くさい数値的な計算で、そういうものを残しているんですね。
他方ニュートンは、書いた印刷したものとしても残したものはあります。その中で最も有名なのは、“Principia Mathematica Philosophiæ Naturalis”という本で、ラテン語で書かれているんですが、日本では“自然哲学の数学的諸原理”とに訳されています。数学的原理Mathematicaという言葉が入っているんですが、Mathematical Principles of Natural Philosophyて言えば英語としてわかりやすいかもしれません。ニュートン自身が“自然哲学”っていう言葉を語っていること自身が、一般の方にとってはわかりづらいことだと思います。ニュートンに先立ってデカルトという有名な哲学者であり数学でもちょっとした仕事をしている人ではありますが、デカルトは、ニュートンから見ると、非常に粗雑な議論を飛躍だらけのロジックで展開した人であったわけですね。ニュートンはそれに対して、本当に数学的に緻密に議論を組み立てるということをやっていた。ニュートンがそれができたのは、ニュートンが力学と同時に近代数学の花ともいうべき微積分法の核心を発見したからで、日本ではよくライプニッツとニュートンが同時に発見したとか、そういうことがよく話題になります。これは面白い話ではあるんですけど、私から見ると大した話ではなくて、数学としてはニュートンとライプニッツは比較にならないくらいニュートンが深い。乳ニュートンはものすごく深いところまで微積分法というものを独力で発表もせずに1人で大発見していたわけです。本当に驚くべきことなんですね。その驚くべき微積分法の発想をベースに置きつつ、彼は有名な“自然哲学の数学的原理”Principiaと言われる本を書くときには、なんとその微積分法の方法を全く使わずに、本当に古代の幾何学の立場で書いているんですね。日本で多くの翻訳が出ていますが、その翻訳を読むと楽しいっていうふうに言った人が、かつて評論家あるいはジャーナリストにいますが、ベトナム戦争にもそれを運んでいって感動して読んだって言うんですが、私は嘘くさいと思うんですね。それは英訳で読むとしても非常に難解な本で、そこに展開されている論理っていうのは全部幾何学的な言語で展開されていますから、それをフォローするってのは容易なことではないんです。今の私たちだから容易でないのか、今の私たちでも容易でないのか、これは議論のわかれるところだと思いますが、少なくとも私たちが使うような現代数学の簡単な言葉ではない。もうとにかく古代の数学の立場を使って書いている。ニュートンはおそらく自分が古い数学の言語で書くことによって、同時代の人々でも少しは自分の発見の意味がわかってくれるだろうと、そういうふうに思ったんじゃないでしょうか。実際アイザック・ニュートンは、単に孤高の人というだけではなくて、その知性を認められて、”Let Newton be”、詩人をしてそういうふうに言わせたわけでありますから、本当に同時代の人々の中で、知識人のエリートです。神様は神の創造の秘密を人々に示すために、ニュートンを産んだのである。ニュートンが出たことによって、私たちの世界は神の創造の秘密、その創造というのは神のCreationですね。私たちは神の被造物作られたものcreatureでありますが、creatureであるとこの宇宙・人間をニュートンを通して明らかにしようとしているんだと。神様のことですから明らかになさろうとしているんだというふうに日本だったら訳すべきところでしたよね。そういうふうに言わしめたニュートンの見識というのは、ものすごく幅の広いもので、だからこそニュートンはなんと今で言えば日本銀行でしょうか、それの長官という役職まで与えられるほど重要であり、サー・アイザック・ニュートン、サーという貴族の称号までいただくことになるわけであります。
要するに、学問人として立派であるということが、世界のこと、地球のこと全てのことについて、「ニュートンに相談してみたい」というふうにみんなが思う。そのくらい深い学識を示していたわけです。私が今述べたことと、20世紀以降の“専門”という言葉がいかに意味が違っているかがおわかりになると思います。20世紀以降“専門”というのは、蛸壺という日本語で表現される世界があるように、小さな自分の狭い関心事を生涯を通じてずっと研究している人を“専門”っていうふうに呼ぶようになりました。学問の世界が専門に分化していくということは、専門家にとっては、言ってみればそれぞれの分化した専門のプロフェッショナルにすぎないということになるわけですから、その「専門についての知識をもって世の中のことを全てわかる深い見識を得られるというわけではない」ということですね。専門家というのは、その筋の細かいことをやたら知っている。例えば私の友人の中に鉄道の大好きないわゆる鉄ちゃんという人がいるんですが、そういう鉄ちゃんになると単に鉄道の写真を撮るっていうのが好きだっていうんではなくて、もう本当に訳のわからんものに凝るんですね。キハ60何とかとかそういうなんかよく私は知りませんが、その呼び名の中で珍しい汽車があるとか、機関車というのは連結器っていうのがあって、昔だったらスチームの力で今電気の力でカチャっと握手をするように、連結してるわけですね。連結器に関しても時代の長い変遷があるようで、そういう歴史を踏まえてこの連結器はとても珍しいとか、そういうふうにいわゆるオタクっていうやつがいるわけです。それはそれはものすごい深い知識なんですけど、だからなんだ。私はそういう人と一緒になると、「長岡先生、この連結はすごく珍しいんですよ」とすごく嬉しそうに解説してくれるんですが、私にとっては何も嬉しくも何でもないし、連結器によって電車乗り心地が変わるとも私なんかわからない。私にとってはどうでもいい知識なんですね。でもどうでも良いような知識であっても、それを突き詰めていくという人生の生き方に、ある種の面白さがあるということを私は認めるにやぶさかでありません。本当に素晴らしい専門家という方の中には、そういういわば世間ずれした、本当に少年のような心のまま、おじいさんにまでなった偉い学者さんもいます。そういう方が生きていることそのものが清々しくて、素晴らしいと思うんですが、Academicianとしてその方に政治のうんちくを語ってもらいたいと思うかっていうと、やっぱりそうはいかないというところがあります。言ってみれば、その専門ではずっと頑張ってきているけど、専門外のことについてはわからない。専門家の専門家たるゆえんは、専門外のことはわからないと言えるということなんですね。
私がこのスモールトークの中で何回かお話してきたことですが、医学が進歩したなっていうふうに私はつくづく思うのは、医学の専門家たちが「それについてはわからない」っていうことがはっきり言えるようになったことです。一昔前はお医者さんは何でも診断をしていました。しかしながらそれがわからないということが言えるようになった。これが素晴らしいことです。ところが、私たちはそういう多くの専門家に囲まれた現代というありがたい時代に生きながら、専門家に専門外のことを聞いて、あるいは自分の関心事を聞いて、自分の思う結論を補強してもらいたがっている。そういう傾向があるのではないでしょうか。政治家が有識者会議というのを開くのは、まさにそういう目的のためで、実は政治家が導いてほしい結論を専門家たちも合意してくれる。こういう会合なんですね。本来であれば、本当にAcademicianと言われる日本学士院が意見を言う。あるいは学術会議が意見を言う。これが素晴らしいことなんですが、それは政治家の意に沿わないので、政治家や官僚が自分が言いたい結論を上手にまとめてくれるために、いろんな委員会を組織する。私は「委員会行政」っていうふうに呼んでいますが、日本の最も腐った構造を作ってきたんですが、かつては官僚が優秀であったために、委員会行政でも民主的な運営を装いながら、優秀な行政政策を立案することに成功してきたと私は思っています。しかしながら、最近はその政策をリードすべき官僚と言われる人たちが広告代理店レベルになってしまって、そして広告代理店レベルの有識者会議を組織して結論を誘導している。そして国民を黙らせる。という構造になっているということです。
私は、今のような専門家は本来の意味での有識者ではなくて、専門家に過ぎない。専門家には専門以外のことを聞いてはいけないということ。そのことが、20世紀以降悲しい現実として存在しているということを、私たちは知らないとなりません。自然科学においても、かつては湯川先生とか朝永先生、物理学の世界ですね。そういう本当に立派な方がいらして、ありとあらゆる分野に精通していらっしゃった。数学で言えば、高木 貞治先生っていう方がいらして、数学者としてもものすごく素晴らしいのですが、文筆家としても素晴らしかった。そういう方々がいらした。もっと古く遡れば寺田寅彦とか、そういうような人もいますね。もっと物理学の研究で素晴らしい物を残した人もいます。偉い人のことを言い出したらきりがありませんが、そういう偉い人が活躍できた時代と、言ってみれば本当に小さな専門に閉じこもってその中でコツコツとやっていかないと良い仕事ができない時代に入ってしまった20世紀と大きく違うということです。私たちは、専門家というのが20世紀においては専門分化が進みすぎてしまったために、専門的な知見は信頼できるけれども、それをちょっとでも外れた意見を求めることはできないということを、知らなければいけないと思います。
例えば、ワクチンを打ってもらうお医者さんに行って、「このワクチンどういうふうにして効くんでしょうか。どういうふうにして開発されているんでしょうか。」そういう質問をする人はいないと思いますが、質問したところでまともな答えは返ってくるはずがない、なぜならばそんな専門については全く知らないからです。ある意味で、大衆的な大ワクチン接種が行われたわけでありますが、十分な科学的なエビデンスも揃ってない段階で見切り発車したわけでありますが、そのことについては医療の関係者たちはみんな押し並べて慎重であったはずです。その意見がかき消されていく過程を、私たちはテレビなどの報道を通じて、知っているわけですね。いかに専門家の意見が潰され、専門家と言われる人々によって有識者会議というのが開かれ、その会議を積み重ね、どこで決まった結論だかわからないような結論が最終的にまとめられ、行政として執行されるという仕組みになっているのか。日本社会の構造もそこに見ることが、垣間見ることができたんじゃないかと思います。
今ウクライナ問題を通じて、いろいろな専門家がいるもんだなということを改めて思い知らされる思いでありますが、立派な方もいればかなりいい加減な「なんちゃって専門家」の方もいらして、テレビ局のプロデューサーやディレクターのレベルもやはり様々なというふうにつくづく思いますが、そういうことに関連して、専門家とか職業人と言われる人と、本当の意味での見識深い賢人、昔賢人会議なんてのはありましたね。ローマクラブなんてのもありました。そういう賢人会議、日本学術会議のような世界に東大卒業生が大きな割合を占めているのはおかしいとかっていう馬鹿な議論が、あるいは東大の先生が多いという軽薄な議論がまかり通るような世界に今私たちは面しつつあるわけでありますから、ますますもって専門家という言葉、あるいは大学教授という言葉に対して警戒を怠ってはいけない。と同時に、大学教授は自分の小さな専門を子供の頃のような気持ちで大切に守りながらずっと追求している。そういう気持ちの人もたくさんいるということ。それはそれとして、本当に尊敬に値し、愛するに値することであるということを考えていただきたい。そういう私の願いと一緒にお伝えしたいと思いました。
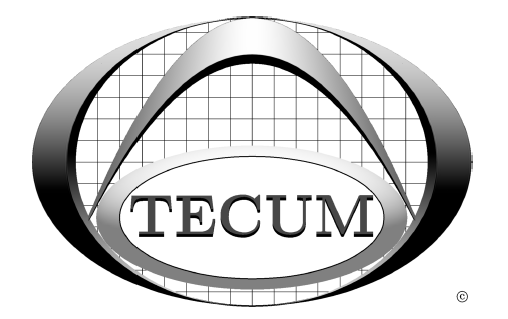
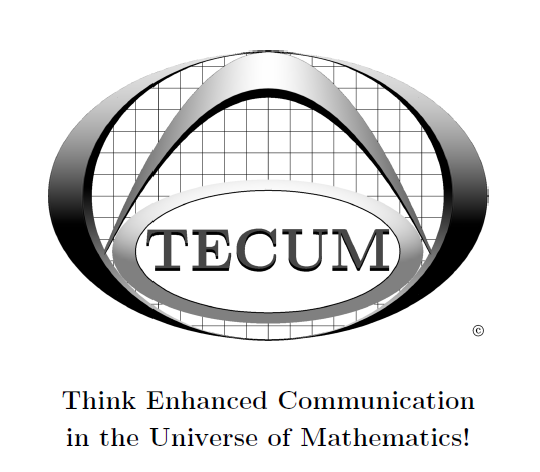

コメント