最近のわが国では、「親が、子どもに深く関心を持って関わることは、当然である」という風潮が、一般的になっています。もちろん子どもの問題に関しては、親は最後までそうでなければならないとは思いますけれど、子どもの教育問題、とりわけ子どもの学校問題に関して、最近の家庭では親があまりにも強く関心を持ち過ぎている。そのことが弊害にさえなっているという印象を持つことが少なくありません。なぜならば進学、次のステージの学校へと進むときに、いわゆる良い学校とたいして良くない学校、悪い学校、そういう学校の良し悪しが、一次元的な尺度でもって考えられていて、その中で自分の子どもが最も良い学校に進学できるように、親たちは一生懸命頑張る。親がいっくら頑張っても子どもが頑張らなければ意味がないわけですけれど、親たちは子ども頑張らせるために良い進学対策、それを保証してくれるような教育サービス、それを購入する。あるいは、どれが良い教育サービスであるかっていう情報収集に奔走する。そういう光景がいまだに目についています。
他方、政府の方では、少子化対策に対して、異次元の対策を打つというわけのわからないことを言っておりますが、それほどに少子化問題は深刻であるわけで、少子化問題が深刻なのは、例えば少子化に応じて、子どもに対するサービスが縮小していかない限りはサービス過剰になる。わかりやすく言えば、学校の先生も学校も減らなければ、少子化対策に対応しないわけですね。そうなると失業問題とか倒産問題に行き着かざるを得ないわけですから、それを防ぐために、1学級の定員を今よりもずっと少ない数で運営できるようにする。1学級20人を最大にしようとか、そういうような話が出てくる。
前に取り上げた話題ですが、最近の少年少女、あるいは青年は、「集団の中で本当に自らを磨き上げる」ということが不得意なり、集団で行動すると、まるで全体主義国家で教育を受けている子どもたちのように、本当に統一見解を持つ。そういう統一見解を持たない人間を、「空気を読めない奴」と言って排除する。それが「いじめ」という非常に卑劣な行為にまで及ぶ。こういったことは、私は小学校低学年ではありうるかなと思っていましたけど、実は中学や高校や最近では大学に入ってもそういう「いじめ問題」がある。いじめられる対象が、勉強ができない子どもたちではなくて、勉強が得意な子どもたちに対して、「空気が読めない奴」ということでいじめがまかり通るようなんです。そういう意味では、そういうくだらない「いじめ」がないような、良い教育環境を子どもたちに与えてやりたいと思います。心から思いますね。そういう「いじめ」にあって、本当に悩んでいる子どもたちは決して少なくない。その問題に深く関わってくれる先生たちも決して多いわけではない。むしろ戦前の日本と同じように、異質な才能を持った人間に対して、先生も寄ってたかっていじめる側に入ってしまう。そういう傾向があると最近聞いて、私は心を痛めています。
本来、学校は楽しくなければいけない。本来、学校は毎日毎日行く意味があるということを、子どもたち自身が発見するような場でなければならないと思うのですが。今は人生を生きていくためにどうしても避けて通ることができない学校という制度の中で、うまく生き延びるということを学ぶ。そういう言ってみれば最低の教育の場、非人間的な教育といいましょうか、「人間が人間らしさを取り戻すための教育」ではなくて、「人間が人間らしくなる、人間らしくなるようにどんどんどんどん追い詰める。」そういう言ってみれば「調教の場」になっているように思います。そして、そういうのはよくない教育でありますから、良い学校というのはそういうことない、本当に子どもたちが伸び伸びとする場であるはずなのに、そのことがきちっとわかっている両親や学校の先生は実に少ない。全く無責任なランキング表とかっていうのを発表する受験ジャーナリズム。「その報道にそのまま乗っかって踊らされている。」ということに気がついている人はごく稀ではないでしょうか。
むしろ戦前のように、いろいろな意味でのエリート校っていうのが、そのピークがたくさん存在していた。例えば誰でもよく知っているように、国立大学には帝国大学っていう特別のランキングの大学がありまして、7帝大といったものであります。北海道、東北、東京、名古屋、京都、大阪、九州、そういう伝統を持った学校、それが今も普通の国立大学として続いています。大きなキャンパスと大規模の教授陣を抱え、立派な大学ですね。それが良い大学かというと、それは必ずしもそうは言えない。今の東京一極集中という文化的な傾向、あるいは社会的な傾向を反映して、地方の衰退はもう歯止めが利かないくらいの勢いで進行している。そのことが実は大学入試にも大きく関係しているということは、大学関係者であれば誰でもが知っていることです。いわゆる帝国大学でさえそういう状況でありますから、普通の国立大学であれば、私が子どもの頃とすっかり別の世界が今現実に出現しているわけです。
他方、受験ジャーナリズムのいうところの良い大学っていうのは何か。子どもたち人気のある学校なんですね。子どもたちの人気っていうのは何なのか。例えば大学で言うと、「大学スポーツが強い。」そういう大学に人気があるという説があります。これが本当か嘘かは知りませんけれど、日本の大学スポーツは、学生スポーツは異常ですね。せっかく大学に入ったのに、それはスポーツ学部に入った、体各部に入ったと、その専門家になるというなら話は別ですけど、そうではない一般の学部に入った学生が、課外活動に自分の大学生活4年間、それを全部捧げる。これは国際的に見て異常なことです。
日本の大学は学費が高いっていうふうに言う人がいますけれども、それは奨学金の制度があまり充実してないということであって、学費そのものは国際的に見ると、むしろ安いと言っていい。アメリカやイギリスであれば、普通の大学の学費ってのは、とんでもない金額です。日本で名門校と言われている有名な大学も、日本の平均的な大学の2倍以上の金額を学費として取るでしょう。ヨーロッパになりますと、だいぶ状況が違いまして、特に北欧とかドイツなりますと、大学の学費は国立大学であれば無料、とこれが当たり前。なぜ当たり前なのか、それは消費税が高い、税金が高いという社会福祉あるいは福祉政策の一環として、そしてそれを支える「国民の民度を高める。そのために教育が必須である」という考え方から、教育に対する特別のサポート、財政的サポートそれがあるからであります。
日本でもそれなりに学費はしますね。今の日本の平均的なサラリーマンの給与の中から、子どもを例えば平均的に2人として、大学にやる。その学費は大変な金額になると思います。しかも、いわゆる教育サービスをさらに追加的に購入するとなると、それの財政的負担は大変なものですね。その大きな財政的負担を超えて、大学において習得するものがあるからこそ大学に行かせたいと、親は思うのでしょうが、果たしてそれがペイする、つまり、今の流行りの言葉で言えば、コストパフォーマンスって言いますか、コストベネフィットって言ってもいいかもしれません、コストをかけただけ、それだけベネフィットを得られるかということです。もし、スポーツに明け暮れる、あるいは課外活動に明け暮れる4年間であったとすれば、その大学の4年間での活動は、その子にとって生涯にわたってどれほどのベネフィットになるのか。私から見ると、それはむしろベネフィットと反対に、重荷となり、そして勉強しなかったことのツケが終生にわたって、つきまとうわけですから大損する。これは、倒産するに決まっている会社の高い株を購入するようなもので、馬鹿げているわけです。投資としてはですね。でも、日本の親たち、保護者たちは、子どもの進学問題っていうのを考えるときに、「大学のランキング」と言われているものがいったい何であり、そしてその大学の中で過ごす4年間、それに自分の子どもがどのような適性を持っているかということを、判断する力を持っているんでしょうか。
私は、親が子どもを育てるときには、義務は二つあって、「一つは成長するために必要な栄養とか健康に気を配る」っていうことですね。「もう一つは、その子が一人前に生きていく、独り立ちをするために必要なアドバイスを、知的にその年齢に応じて行う」ということだと思います。私自身がそれができてるかって言われると、それは難しいと言わざるを得ないのですが、理想的にはそうだということです。反対に「良い学校とは何か」という定義もわからないまま、世間が言うところの、いわゆる「良い学校」に進学させることが、その子の人生にプラスになると思い込んで、子どもたちをときにおだて、ときに励まし、ときに叱り、という子育てに没頭するならば、時には自分の社会的な活動さえ犠牲にして、あるいは自分自身の勉強時間さえ犠牲にして、子どものためにという名目で、自分の貴重な人生の時間を子どもに対する「指導」、私に言わせれば、指導というよりは、「干渉」というべきですが、それに時間を使うならば、子どもは育つどころか、実はむしろ歪んでいってしまうのではないかと思うんです。
人生は、教育に限られませんが、「良い悪いというのを簡単に決めることができない。」ということを理解することが、「良い悪い」を語る上で、最初の出発点であるという、大人になったら当たり前のこと。そのことを、今の日本の大人たちが忘れていることが、私としては大変気がかりです。子どもたちがそういう社会の流れというものを知らない大人たちの、勝手な振る舞いに翻弄されないようにと願っています。
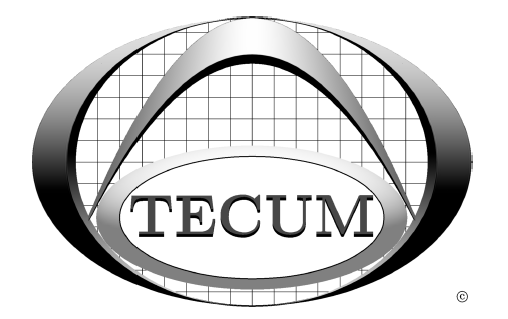
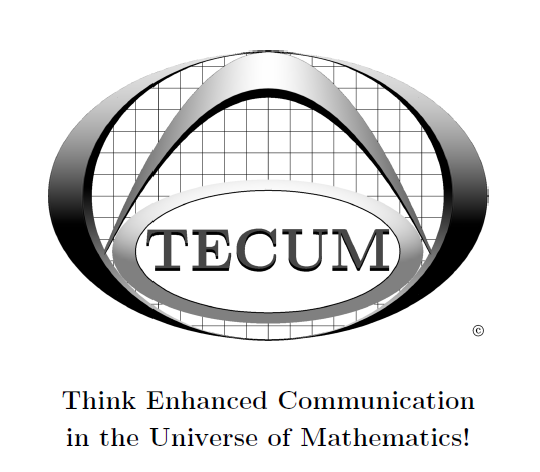

コメント