今回は、「原因と結果」ということについて考えてみましょう。何かが現象が起きたらば、それには必ず原因があるんだと。原因があるならば、必ず結果が起こるんだと。こういう説明の仕方を「因果律」に基づく説明といいます。因果律とは、英語だとcausalityというふうに言いますが、人類が最も古くから演繹的な議論において使ってきた基本原則です。因果律が甚だしく登場するのは古代ギリシャの哲学者アリストテレースにおいてであると思いますが、その後も私達はずっと因果律を用いて議論をしてきました。その因果律に対して、それが変わってきたというふうに私が思うのは、原因と結果が同時に起こるという自然現象。例えば、運動をするときに、運動を起こるとき、あるいは運動の加速現象が起こるとき、力が働いている。力が働くと加速度が生ずる。逆に加速度が生ずると、力が働いている。こういう場合には、どちらが原因でどちらが結果というのを、明瞭に区別することができないのではないかと思います。
数学的な世界像の中で、最も特徴的なのは微分方程式と言われる方程式A=Bという方程式、それのちょっと複雑なバージョンですね。A=BっていうときにはB=Aでありますので、微分方程式という等式であると、左辺と右辺との間に本質的な区別ということをすることができない。この微分方程式による自然現象の叙述、これが始まったときに、いわば因果的な説明ではない新しい説明の方法を、私達が獲得した。なんと17世紀のことであります。それから約300年とか400年とか経っているわけでありますけれども、まだ一般の人々の間にまで、この画期的な説明の方法が人類文化の中に根付いたということの意味は、理解されていないのかもしれないと思います。
つまり、依然として因果律で説明する。ということが当たり前になっている。そんな印象を受けるわけです。特に最近では、生化学と言ったらいいんでしょうか、biochemistry、体の中でいろいろな機序で働いている化学物質、それの詳細な機序メカニズムが解明されてきている。これは画期的と言えば画期的でありまして、その代表的なのはドパミンとかドーパミンと言われるもので、これはアメリカ映画なんかを見ていると、日常的な場面でもよく使われていますね。ドーパミンが分泌されてすごく体が元気になっている。頭脳が活性化している。肉体がフルパワーに達している。そういうような言い方がなされる。アスリート中でさえ使う人がいます。あるいはそのアスリートをコーチする人が、こういう化学物質の名前を口にする。この化学物質、これが人間の生態系中で、人間に限らず動物の中で、重要な神経伝達物質として重要な役割を果たしているということについては、20世紀の科学的知見で十分証明されていることでありますが、ドーパミンが分泌するということで、なぜ人間の体が元気になったり、頭脳が明晰になったり、いろいろと良いことが起こるのかということについては、ドーパミンが次々といろいろな物質を作り出すのを刺激するというふうに、より詳細なメカニズムを解明することによって、それができるとみんな信じており、先端的な基礎科学の研究者たちはそれを一生懸命詰めているわけですが、そのように詳細化すれば詳細化するほど、私は、謎は深まるのではないかという科学の常識を、改めて確認したいわけです。
私達は17世紀に微分方程式という数学的な手法によって、自然現象をミクロのレベルからマクロのレベルまで、宇宙のレベルまで解明するということができるということに成功しているわけですが、そのように私達が、例えば人間の生体の中で働く化学物質、あるいはその化学物質が伝達するところの例えば神経系という体の組織、それによって突き動かされているというふうに信じ込んでしまうのは、少し楽天的すぎるのではないかと思うのです。例えば、元気が出るというのはまさに気が漲るということでありまして、「気が漲る」という古代中国以来の言葉を使う代わりに、「ドーパミンが分泌される」という方が科学的であるというふうに感じてるのは、やはりちょっとおめでたいことでありまして、ドーパミンの分泌がどのような細かい機序までわかるかということには興味がありますけれども、結局のところ、それは最終的には「元気が出るのはなぜか。」というところ。それは私の知る限り、まだ説明ができていないように思うんです。
同様に、「痛み」についてもそうですね。痛みというのは、痛みの伝達物質というのがおそらくあって、私は圧迫骨折をして以来、腰痛に悩まされる日々でありますけれども、それは言ってみれば肋間神経というのが頭脳に対して、私が腰の部分に痛みを感じているということを、信号で知らせている。そのことの結果であって、本当に痛みとは何かということについてはあまりよくわからない。あまりわからないだけではなく、おそらく今ペインクリニックという分野も成立しているようですが、おそらく全くわかってないのではないでしょうか。人間にとって痛みというのは、死と同じように、言ってみれば最終的な悪というか、人間にとって最も厳しい敵でありますね。痛みから解放されるということ。それは死から解放されるということと同じように、古くから人類の夢でありました。
生来病苦というふうに言いますが、人間の生きていく上で本質的な苦しみ、病とか死とか、それがやはり苦痛と結びついているというのが、人類がそれを恐れてくる最大の理由だと思います。死というのは、とりわけ脳の死あるいは細胞の死というのは辛いものであるということを、私は加齢黄斑変性という病気の初期の治療で、光力学療法というふうに当時呼ばれていましたが、荒っぽい治療で、古典的にはレーザー光線を当てて網膜を焼くという、そういう手術であります。その手術を受けたときに、痛いはずはないのですが、ものすごく辛い思いをしました。それは、脳細胞の末端にある視神経を殺される、焼き殺される苦しみだったと私は考えているんです。それはお医者さんたちには言っても通じない話だと思います。なぜかというと、お医者さんたちは自分たちの地位視細胞を殺した経験は、たとえ眼科医であってもご存知ないと思うからですね。どんな手術でも完全麻酔で、全身麻酔と普通言いますが、やらない限り、ある種の死の痛みっていうか、ある部分を殺される痛みを伴います。それは怪我をしたときの痛みというのとは違う、本当に深い深い痛みですね。
その深い深い痛みを感じているのは、脳であるのか。それは脳が痛みを感ずる指令を出していることは確かであろうと思います。神経そのものが痛いわけではないし、神経が、ここが痛い痛いと言っている部位、それが本当に痛いのかどうかよくわかりません。私が、それがよくわからないというふうに知ったのは、肋間神経にしても、顔面神経にしても、ここが痛いという信号を脳に発するのですが、しばしば誤信号、誤った信号を脳に送るんですね。顔面神経の場合は、私はよくある病気だと副鼻腔炎のようなものですね、それのちょっと悪質な場合でしたけれど、それで私は最初歯が痛いと思ってました。そのうちに耳が痛いとか、目の裏が痛いと、とにかくいろんなところが痛くなるんですね。いろんなところにはそれぞれ痛くなる原因があるかというと、例えば歯医者さんは「ここの歯はもう直っています。全然そう痛いはずはありません。」そういうふうなことを言ってくれて。その歯医者さんが名医だったおかげで、その歯医者さんが耳鼻科に行きなさいっていうアドバイスをしてくれたというのが、私にとってその病気を克服する大きなきっかけになったのですけれど。痛いと思っている部位が痛いのではなくて、痛いっていう信号を脳に送っている。そして脳はその痛みを、痛み全体として、痛みそのものとして知る。痛みとして知るということがどういうことなのか。本当はよくわからないんですね。私達の人間の触覚のように、かなり解明されているものもありますけれども、痛みというのは触覚の一つには違いなく、例えば、ホットソースをなめたときの辛さというのは、舌の味覚に感ずる痛みの感覚なんだそうです。しかし、そういう痛みから神経を焼き殺される苦しさの痛み、痛みのバリエーションは非常に豊かで、中には肩こりから、ものすごくひどく痛みを体中に感ずるそういう人もいて、痛みから人類を解放するというのは、本当は医学の夢だと思うんです。これを、麻酔剤を使うことなく、あるいは習慣性ができてしまう、そういう麻酔剤を使うことなく、日常生活を健全に送れるような形で、痛みを取ることのできる薬、これが普及すれば何とも有り難いことではありますが、それはきっとできないのでしょう。痛みを通して私達は何かを学ぶ。ですね。何を学ぶのか私自身も多くの痛みの経験をしてきているんですけれども、その結論を得るには至っていません。
しかし、痛みに関する医学的な書物を読んでも、あるいはそのような情報をインターネットで調べても、痛みそのものについての考察で、哲学的な厳密性にまで到達しているものは全くないと言っていい。いわゆる疼痛を和らげるための薬は、いろいろと開発されてきています。この意味では、ペインクリニックというふうに言っている人たちも、結局のところ薬理の専門家が開発した疼痛の神経をブロックする、そういう薬をうまく使うという技術者に過ぎない、と思うんですね。かつて、外科と内科は、その医者の名前が片方はSurgeon、片方はphysicianと言って区別されていました。physis(フィシス)自然、あるいは体そのものは使うのは内科であったわけです。痛みっていうのは本来、まさに内科的な病気で、外科的に治るものでは決してないと思いますが、その内科において、それを診断し、ちょっとした薬を処方することによって体質を改善するというような、生易しいものでは到底追いつかないくらい、痛みは激しいわけです。その激しい痛み。それをブロックしてくれる「神経ブロック」っていうのは、痛みの伝達を妨げるそういう物質として開発され、それによって脳に痛み信号が到達しない。だから痛みを感じない。そうなるんですけど、痛みがなくなっているわけではないんですね。痛みを感じなくなっているというだけです。つまり、痛みの解消ではないということです。
皆さんの中には痛みっていうのは主観的なものなんだから、主観的に満足すればそれでいいじゃないかと、そういうふうに思う人が少なくないと思いますけれども。私自身は現代の先端科学の盛んな時代に生きる人間の一人として、できたらば、痛みそのものに対してもう少し接近したい。その本質を少しでも深く理解したい。単なる対症療法は私にとってはどうでもいい。でも、「痛みとは何か。」という深い深い問題。これを私は避けて通るというのは、一時的には痛いからととりあえず助けてくださいっていうことはあると思いますけれど。でも、本当に大切なのは結局のところ、痛みから解放されるには、私達が灰になる以外にないということであるとすれば、それは痛みの研究としては敗北であると。
私達が、嬉しいとか、感動したとか、楽しいとか、幸せだ、気持ちいい、そういう肯定的な私達の感覚と同じように、辛いとか、痛いとか、惨めだとか、「そういう気持ちが一体何によって、どのようにして起こり、それが本質において何なのか」ということについて、かつて文学者たちは、あるいは心理学者たちは様々な場面を想像することによって、あるいは様々な実験をすることによって、そういう問題に少し迫ってきたと思いますが、まだその迫り方は到底20世紀の水準に達しているとは思えない。科学、自然科学、物理学などで言えば、ようやく17世紀の初期の段階に達したというレベルに過ぎないと思うんですね。それはそれだけやはり生命体っていうのが、宇宙や物質と比べると難しいからであると思います。難しいんだからわかりっこないと終わりにするのではなく、その難しい世界に挑戦する人々が出てきてほしい。きっとそういう難しい問題は簡単に成果を上げることができないと思いますけれども、そういう難しい問題を解いてこそ科学者という尊称にふさわしい人として、自分の人生を他の人々の人生の充実に真の意味で役立てることができるのではないかと、私はこれからの世代の人に期待しています。
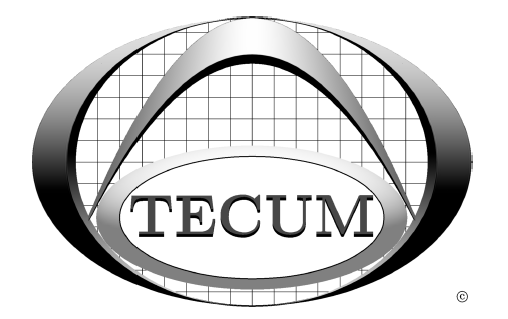
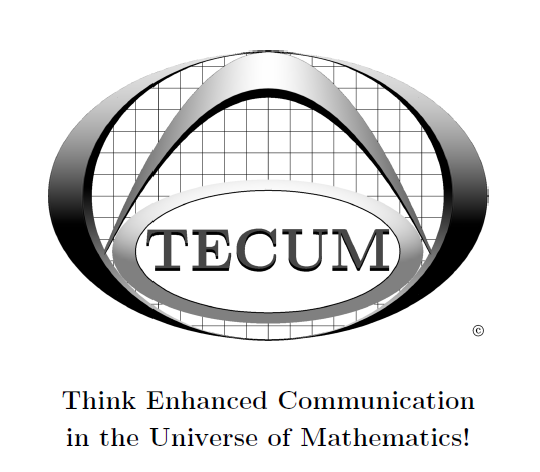

コメント