いろいろな教科の中で「数学は嫌いだ」という人、反対に「数学がとても好きだ」という人、意見が極端にわかれるのが、数学という教科の一つの特徴でありますけれども、私はそのように極端にわかれることが、どちらの側の人にとっても少し不幸ではないかと思うことが少なくありません。今回はそれについてお話したいと思います。
なぜ私がそう思うかというと、「数学が嫌いだ」という人の嫌いである理由、その一つの理由としても、また「数学が好き」だという人は数学が好きだというふうに思う理由の一つとして、両方の理由として共通に挙げられることに、「数学では答えが一つに決まるから」というのがあるように思います。答えが一つに決まる。ということは数学のある意味を端的に表現しているとも言えますが、一方で数学について多くの人が持っている非常に大きな誤解、それを誇張して伝えているような気も同時にいたします。
どういうことかというと、「数学は答えが一つに決まる」。それは多くの人が思うように「1+1というのは2になるに決まっている」、「2+1は3になるに決まっている」、「2+1は4になることはないでしょう」と。4だったら間違いですよね、「1+2は必ず3」です。それが数学の世界だと。それに対して、数学以外の世界では、「1+1が2でない、とそういう難しい、理屈では割り切れない世界のことを扱うんだ。」そういうふうに言う人がいるのですね。中にはそれを自分はデジタルな人間ではなくアナログな人間であるから、という訳のわからない言葉遣いをさらにそれに付け加えたりする、そういう人もいます。デジタルとアナログというのは、信号伝達の方法として本質的に違うものでありながら、実は技術的な基盤として本質的に同じものを含んでいる、ということにさえ注意がいってないということは、デジタル・アナログの議論をするときに取り上げたいと思いますけれど、とりあえずここでは「数学では答えが一つ」ということがどういうことか。これについてちょっと考えてみたいと思います。
確かに数学で、「1+2は何ですか」という小学校一年生の勉強する問題として、それが出題されたら「1+2は3である」と答えると○で、「1+2は4である」と答えたら×である。こういうふうに、正解と誤答・間違い、それが明確に判定され、そして判定された側も、確かにそれは私が間違っていましたと深く納得する。それが例えば、大学入試レベルの国語などの問題で、「筆者の言いたいことの中で、次のうち一番それに近いものはどれか選びなさい」なんていう問題。あるいは下線が引いてあって、「その下線部の言い換えとして最も正しいものはどれでしょう、選びなさい。」こういう類の問題は、例えば5個の中から1個選択すると、五者択一というような形で出題されるときに、絶対これはまるで違うというものがある反面、どちらとも言えるなと思う微妙な選択肢が用意されていることが少なくありません。これは、私は国語の出題として大変に残念なことで、要するに一番重要な本質的な事柄がわかってさえいれば完全に正解が出る。あるいは、これを正解が選べないようでは全くわかっていないというふうに断定してよい、というような問題ならばいいんですけども、曰く言い難いというような表現にあるように、何を言ってるのかよくわからない、どちらが正しいという理屈を立てることもできる。そういう曖昧な表現について、その曖昧な基準のまま、こちらは正解であり、こちらは誤答である。こういうふうに断定する傾向っていうのが、学校国語の中には存在しないとは言い切れませんね。全ての国語の教育がそんなに馬鹿馬鹿しいものではない、と私は信じたいとは思いますが。いわば国語というふうに分類される教科の中には、叙情的な趣でそれを理解するとはどういうことかというような、そもそも正解が何であるかがよくわからないような問題を平気で出題する。そういう一種の文化的な傾向っていうのでしょうかね。
私はむしろ私自身は、この日本の教育の非常におかしな間違い、それの因習的な伝統というか文化というか、そういうものだと思うのです。本当は教育においては、少なくとも大学受験レベル以下の教育においては、やっぱり白黒がはっきりする合理的な理由で、これが絶対に正しい、これが絶対に間違っていると、そういうふうに合理的に判定できるという問いのみが出題されるべきで、その部分だけを取ったならば曖昧にしか答えられないというのは、実は本当は回答の選び方が正しいか間違っているかじゃなく、問題の立て方が悪いというだけだ、と私は思うんですね。数学の言葉で言わせてもらうと、数学は正しい問題として出題されたときに、答えが一つに決まるように出すわけですが、それを「well posed」正しく出題されているといいます。それに対して答えが一つに決まらないような問題、数学の中には、そういう問題もとても良い問題としてあるわけですね。しかし、そういう問題は問題そのものが正しく設定されてない「ill posed」、well posedでないということでill posedというふうに言いますが、数学以外の教科の中にはしばしばill posedな問題を出題して、それがいかにもwell posedであるかのように解説することが、国語ができるということの証明のように張り切って演説する。そういうタイプの先生がいらっしゃるようで、私は、それは大変残念なことだと思います。
例えば、叙情あるいは情緒、それを問題とするときでさえ、その情緒として出題されるべきものは、万人に共有されるべき情緒であって、その万人に共有するべき情緒の表現として、どちらの方がより適格であるかというような問いであるとしても、それは万人が全て、こちらの説明の仕方がより簡潔でより平明である、よりわかりやすい、より説得力があると、万人が納得する。そういう合理性をあるいは普遍性universalityを持っていなければいけないと思うのですが、残念ながら数学教育を厳しく受けたことない人たちの世界では、そういう曖昧な説明の中に正解を求める、あるいは誤答の中から正解を選ぶ、そういうテクニック、それを磨き上げることを求める。そういう風潮が残念ながら残っているようで、私はそれをその戦前の軍国主義文化のようなものだと。日本の輝かしい文化の歴史の中で、やはり私達が現在の汚点として、本当に深く反省しなければならないものだと私自身思っているんですけども、それをむしろ誇りにしてる人たちが世の中に存在するということは、私も認める。やぶさかでない。つまり、認めざるを得ないところであります。
しかし、それは数学以外の教科の中に問題を出題するときに、ill posedな問題を出題して平気な先生がいる、というだけのことであって、それは教科の特性上、ill posedな問題しか出題できないということでは決してない。well posedであって、しかも決して簡単に答えが出せない、そういう問題も出題できるわけです。しかしそういう問題を出題するのは、立派な学識を持っている、あるいは深い見識を持っている、そういう人だけですから、なかなか数学以外の教科においては、そういう問題に接する機会に多くの人が恵まれていない、ということが言えるのではないかと思います。反対に、数学という教科では、実は下手な出題であっても、みんなwell posedな問題のように見えてしまう。あるいは多くの人が、それを問題がill posedであるということに気がつかない。そのためにill posedな問題であっても、答えが一つに決まる。そういう思い込んでいる。そして、それを思い込んで信じ込んでいる先生が、その採点基準に従って採点するということに、人々が文句を言わない。これが一般的だというに過ぎない。
もし皆さんが高校生以下で特に反抗期の少年少女たちであって、先生たちの言うことが正しいとは限らないということが言えるような年齢になっているならば、そしてそのようなことが言えるだけの十分な論理性を自分自身の中に培っているならば、数学の問題といえども、答えは一つでないと、いくらでも言えるんですね。特に学校数学の、例えば中間試験とか期末試験などで出題される問題に関して言えば、揚げ足を取ろうとすればいくらでも揚げ足を取ることができる。もっと良い言い方をすれば、問題文の厳密な解釈の仕方によっては、答えがいくらでも他にありうるという問題ばかりだ、と言ってもいいくらいなのですね。そのようないろいろな解釈の中で、このような解釈をとるならばこういう答えになる。違う解釈をとるならばこのような答えになる。そういう答えの可能性を、自分自身の中できちっと構築することができるようになれば、数学ほど皆さんにとって身近で親しみやすいものは少ない。というくらい数学の身近さを実感してもらえると思うのですが。
「数学は答えが一つである」というのは、答えが一つであるように問題を設定している。あるいは、実力のない数学の先生であっても、問題集の真似をして問題を出題すると、それがwell posedな問題のようにしばしば見えてしまうということの結果であって、本当に厳しい数学的な批判精神を持ってきて、高校以下の教科数学で、「数学は答えが一つだから」というふうにもし言う人がいれば、私はそれはチャンチャラおかしいと言ってやりたい。それは答えが一つであるように、問題の解釈を固定的に決めている結果に過ぎない。問題を支えるための様々な前提についての無知の結果に過ぎないと、申し上げたいわけですね。
しかしながら、私達の様々な知恵、それが私達の多くの無知によって支えられているという、いわば学問の最も重要な基本原理。そのことに皆さんが目覚めれば、私達が数学の問題といえども、実はさらに深い基礎に、今のわかっているということの背景にあるもっとより根本的な事柄に、そういうふうにしだい次第に理解や認識を深めていかなくてはならないということに気づくはずで、そのことが数学を学習する側にも数学を教える教師の側にもわかるというのが、数学の一番の魅力ではないかと思うんですね。
反対に、数学以外の科目では、教科を教える側も習う側も、自分の知識にどこに不完全さがあるか、自分の教育内容にいかなる不完全性が潜んでいるか、そういうことに無自覚で教えることができる、あるいは学習することができる。それは教育や学習が不完全な結果であって、教科が数学のように答えが一つに決まる冷たい科目であるとか、数学の答えが一つに決まる厳密な教科であるということの結果ではなく、単なる教科内容を支える学問的基盤、それに関する無知、そしてその無知に伴う傲慢、自分の傲慢であることに気付かないことの無知ですね。それによるのだと私は言いたいと思うのです。
有名な「無知の知」という哲学的な言葉がありますけれども、実は学問は自分が何を知らないかということについて、どれほど謙虚に反省することができるかということ。そこは学問の学問たる所以でありまして、数学は学問性のいわば規範とか模範として、自分たちがいかに知らないかということについても深く知っている。それがゆえに「知っているということに関しても、より深く知っている」そういうふうに言えるとても貴重な教科だと思うのですが。そのような体験を小学生に対しても与えることができると、いうのは数学以外ではなかなか難しいですね。例えば叙情の世界であって、その叙情の世界の中で、この詩は読みたいね、この詩のここが何とも素晴らしいね、ということを100%の明証性でもって、子供たちと先生が共有する。そのことは簡単に言うことはできますけど、実現することは絶望的に難しいかと思います。
それに対して数学では、「1+2は3である」というのは、「1+1が2である」ことの結果だと。なぜならば、「1+1が2」であり、従って「1+2が3」であるというのは、「1+1+1が3である」ということと同じことなんだ、というような納得。これは小学校一年生でもできることですね。でも多くの人が「2+3が5」、「2×3が6」、それを暗記して終わりにしています。そういう意味では答えが一つだっていうふうに言う人がいるんですが、実は数学的には2+3が5でない世界、2×3が6でない世界が数学にはいくらでもあります。皆さんが知っている足し算や掛け算では、そういう世界がないというだけの話で、数学では「1+2が3でない」ような世界を考えることだってできるんです。
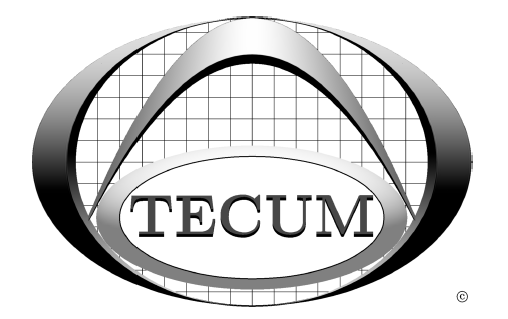
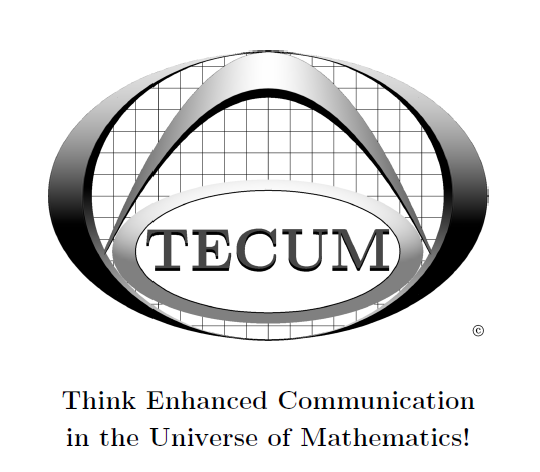

コメント