たまには数学の話をいたしましょう。数学というのは、小学校の頃は最も簡単な話、例えば1+1が2、あるいは2+1が3、そういうところからスタートして3+5が8、11+15が36、こういうような難しい計算へと進んでいくわけでありますね。最初に出会う数学はそのような数の計算だと思うんですが、実は小学校の頃のことをしっかりと思い出してもらうと、皆さん勉強したときには「2+1イコール3」というふうに中学校以上では読む式のことを「2+1は3」というふうに日常用語を使って「は」という。「は」は主語を表す助詞というやつですね。「2+1は3である」。「である」っていう言葉も補うことの方が親切かもしれません。いずれにしても、要するに主語と述語がある、という文章で語ってきているわけです。
そのように考えると、「A=B」という私達が通常使う等式を、小学生の頃は「AはBである」と読んでいるということでありますから、当然Aは主語でBは述語の方に属してるわけですね。だとすれば、「A=Bである」ということと「B=Aである」こと、数学的には「A=B」と「B=A」、これが全く同じではないわけです。相等性というのは本質的に何を意味するのか、ということは非常に厄介な話でありまして、小学校の頃私達は算数を通じて「2+1は3である」というような日常表現を使って数学を勉強し始めました。
しかし、そのような日常表現を使った数学から、次第次第に私達は厳密な論理というのを身につけることができるようになり、皆さんが中学生になった頃は「=」という記号に対して、「A=B」ということと「B=A」ということは同じことである、とこういうようなことを学びます。この「A=BとB=Aは同じことである」ということはそもそもどういうことか。というような少し哲学的な難しい問題は、大学に行って数学科に進むと勉強するわけでありますが、一般にある種の関係、「AとBが関係RにあるならばBとAは関係Rにある」という性質があるときに関係Rのことは「反射律が成り立つ」とそういうふうに言うわけです。相等性、等しさという関係、equality という関係において反射律が成り立つということはなぜなのか、という問題。こんな難しい問題を小学生や中学生の頃考えたことはないですよね。
私達は本当のことがわかっているわけではないのに、にもかかわらず、事柄を正しく理解したと確信し、その確信に基づいて、人の判断が間違っているとか正しいとかということまで断定する。よく言えば応用可能性、悪く言えば傲慢なところがあるのではないかと思います。私達は私達の理解を深めれば深めるほど、私達の依って立つ基盤、私達が論理的に盤石な基盤の上に立っているということの、基盤の脆弱さに気がついてくるわけでありまして、数学の勉強というのはそういう意味でもとても大切であるな、というふうに私は思います。 その大切な数学が、残念ながら人より得をするための技術、いわば経済学的な原理として重視されている今日の状況は、とても残念に思います。歴史に残る多くの古代の文化圏の中で、数学ができる人たちが非常に重視されていたということは確実である、と私は様々な証拠から思いますが、それは数学がしっかりとできる人たちは、誰にとっても公正な判断を最も委ねてよい、そういう信頼できる人である、というふうに思われていたからだと思います。それが現代のように、数学ができる人は人よりも得をする人間である、というふうに思われるようになってしまったら「数学をやる人間なんて碌な人間じゃない」ということになってしまいますよね。私としてはできたら「少しはまともな人間であるな、あんたも」というふうに言ってもらえる人生を送りたいと思っています。
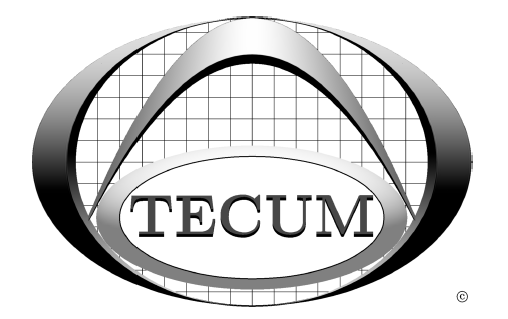
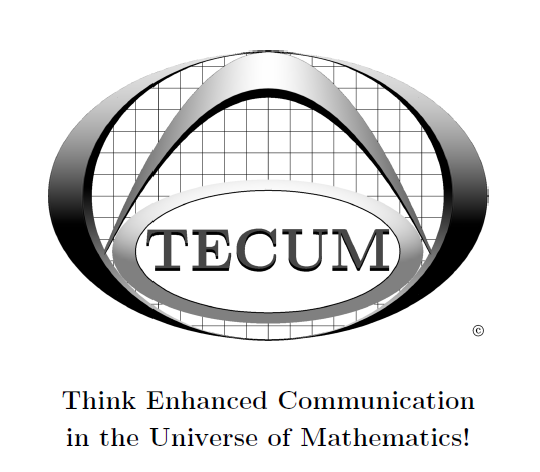

コメント